こんにちは。彫刻科の小川原です。1学期の後半に入って昼間部の実力がグッと高まってきました!中でも何人かは指導に頼ること無く、自分の目で作品の善し悪しを判断し、自分の手で修正していける力がついてきたと思います。作品をまさに「作品」として魅力的にしていくことの意味が分かったら、毎回の制作がきっと楽しく取り組めているんじゃないかなと思います。さらに研究を深めて確実なものにしていって下さい。 まだまだ自分の向かうべき道に迷いがある人も、一つ一つ確実に問題を解決していけば絶対に道は拓けます。闇雲に課題をこなすのではなく、出来ることはしっかりとこなした上で出来ないことに毎回チャレンジしていきましょう!自分に無い新しいものを手に入れようとするなら、それ相応のアクションが必要です!一緒に頑張りましょう! さて、それでは1学期後半の優秀作品を紹介します。 A.Hさんの作品。
ジョセフ。6時間弱での制作です。講評込みで1日描きの課題だったので試験時間分も描けませんでしたが、炭使いが魅力的で内容の詰まった作品になりました。去年の1次試験がジョセフでしたが、受かった人たちの状況をまとめてみると、顔が似てなかったり、炭使いにキレがない(汚い)作品はかなり受けが悪かったようです。顔を似せるのも調子をコントロールするのもどちらも基本中の基本ですが、ぱっと見の印象としては実はそれが最も目立つ要素なのかもしれません。この作品は単純に表現の上手さという点ではまだまだこれからなところがありますが、作者のモチーフに向き合う素直な姿勢が粘り強い観察と作業の積み重ねにつながっていてそれが見るものにジョセフのリアリティを伝えることに一役買っています。
Y.M君の作品。
ゲタの模刻。ジョセフと同じく6時間弱の制作です。こちらも昨年度の芸大の入試で出題された課題でした。かなりバランスをしっかり合わせてこれて、その上で印象も近づけてこれています。ここまでの完成度が出せたら実際の試験でもかなりいい戦いが出来るでしょう。前回の入試では、ほとんどの人が構造(プロポーションや動き、前後左右の形の対応感)にかなり大きな問題があり、まともな模刻になっていなかったようです。ほとんど制作経験の無い像で焦ってしまった部分もあるとは思いますが、だからといっていきなり今までの経験を放り投げて初心者気分で一から組み立てているようでは到底勝負は出来ません。結局は何がモチーフであってもやるべきことは同じだし、求められていることは変わらないので一つ一つしっかり確認しながら形にしていく必要があります。合格者再現作品はどれもかなり印象を捉えていたし、完成度も高かったです。どんな課題が出ても感情に任せてしまうのではなく、クールに、そしてクレバーにやるべきことをしっかりこなしていきましょう。どんな時でも目標値は決して下げてはダメです。
K.S君の作品。

こちらも同じく短時間での模刻です。どんな課題でも結果を出せるようになってきました。非常に頼もしいです。これまではいい目も、そしてそれを表現する力も持っているはずなのに、100%の限界に対して常に80%を目指しているような進め方をしていました。80%を目指しているので結果は上手くいっても75%くらいに落ち着いてしまいます。今はとにかく全てに気を配り、出来ること以上のものが目指せるようになったので、毎回限りなく100%に近い作品が打ち出せるようになりました。粘土に関しては非常に抵抗感が強く、張りを感じる土使いが魅力的です。とにかく常にその時より上のレベルを目指して高めていってほしいです。そして彼はそのおもしろさにきっと気づき始めているんだろうなと感じています。
今年は1学期からかなり高いレベルでクラスを引っ張ってくれる強者が何人も出てきてくれています。夏期講習も盛り上がること間違いないです!
ここで一つ上達する為の秘訣です。一番大事なのは毎回の制作が楽しい!って思えるかどうか、です。楽しいと思ったら努力も苦にならないし、ポジティブに研究を深めていくことが出来ます。
当たり前でしょ!?って思うかもしれませんが、当たり前なんです(笑)
でも考えてみて下さい、今制作が楽しくて仕方ない人ってどれだけいますか?あなたはどうですか?
誰しも事の始めというものは必ずあるはずで、デッサンも習いたての頃は毎日上手くなっていく、あるいは新しい事を覚えていく実感が少なからずあったんじゃないでしょうか?それが次の制作への意欲となって日々の取り組みの糧になっていたと思います。しかしある程度経験を積んでくると指摘される事も目新しい事ではなく、毎回似たような失敗を繰り返し、次の段階に進めない自分にモヤモヤしたりはしていないでしょうか?僕はここが運命の岐路だと考えています。結局今までは新しい事を教わる事(外部からの影響)によって得ていた満足感の実感を、これから先は自分自身で生み出していかないといけないのです。その為には今より上手くなる為に自分で壁を乗り越えていく!という強い動機が必要で、それが持てる人はそのまま上達していって、それによって新たな満足感が得られるのですが、上手くなる為にもう一歩の努力や工夫が出来ない(上がらないモチベーションに負ける)タイプの人はズルズルと同じレベルを引きずって多くの無駄な時間を消費してしまいます。後者のタイプの人もいずれは「最後に自分を上手くするのは自分でしかない」という事に気づき、本来あるべき道に戻って来れるのですが、それは早いほどいいのは言わなくても分かると思います。もちろん分からないことや、技術の習得の為に、是非とも上手く講師を利用してほしい訳ですが、やるのはあくまで「自分」であるという事を覚えていて下さい。
僕たち講師はどんな疑問にも答えていくし、どんな技術でも教えてあげられると思っています。でもそれはただ一方的に「与える」事は出来なくて、僕達が出来る事は「伝える事」ここまでです。あとは皆が「受け取る」ことにどれだけ努力できるかにかかっています。
早いところ上手くなって、自分で答えを生み出して、自分で解決できるレベルを目指しましょう!

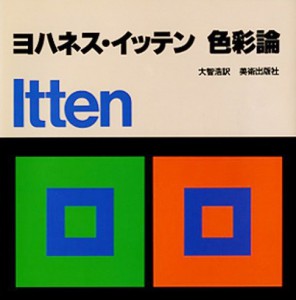
-300x300.jpg)


