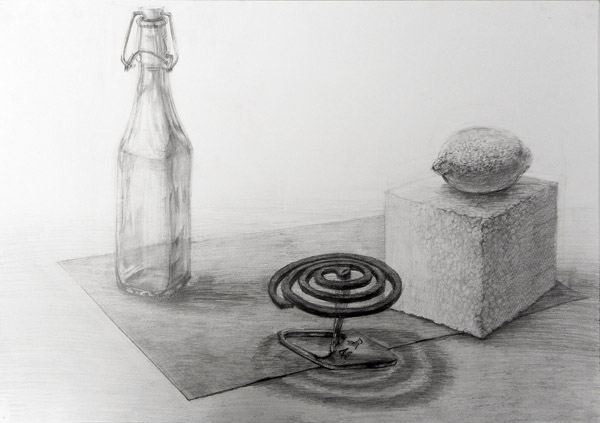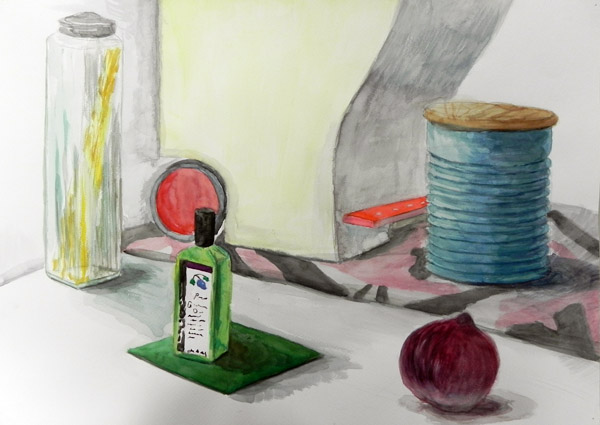こんにちは。油絵科の関口です。
少し暖かくなって、花粉症の人には辛い季節になりましたね。
さて今日は油絵具の色の話をしようと思います。
油絵具の色って沢山種類があって、初めての人は何を買ったら良いか分かりませんよね?長くやっている人でも、意外と色は何となく選んでいる人も多いのではないでしょうか?
10年くらい前に新美の油絵科講師陣で、基本色とは何か?という話になった事がありますが、驚くほどバラバラでビックリした覚えがあります。
「えー、これは必要でしょ?」
「いやー、それは無いよ」
議論したら、今でもそんな声が聞こえてきそうです。拘りの強い講師陣は、好みのメーカーもバラバラで、色によってメーカーを変えている人が多い、というのが特徴的でした。
僕の考える基本色というか、絵を描く上で最低限必要と思う色は以下の通りです。
白
・シルバーホワイト
黄系統
・カドミウムイエロー?※
・オーレオリン
・イエローオーカー
赤系統
・バーミリオン
・カドミウムレッド※
・クリムソンレーキ(又はローズマダー)
青系統
・ウルトラマリンブルー
・コバルトブルー
・セルリアンブルー
緑系統
・ヴィリジャン
・カドミウムグリーン※2
・テールベルト
紫系統
・コバルトバイオレット
茶系統
・バーントアンバー
・バーントシェンナー
・ローアンバー
・ローシェンナー
黒
・ピーチブラック
※ カドミウム系の色は数色ありますが、緑以外は混ぜて作るのが難しいので、好きな色を数色揃えても良いと思います。
※2 カドミウムグリーンはカドミウムイエローとヴィリジャンの混色で作る事が可能です。
パーマネント?とか、コンポーズ?とか、?チントとか、?ヒューとかが名前に付いていない色である事が重要です。茶色系統や白と黒、あと数色を除いて、高い絵の具が多いですね。一度に全部揃えたら軽く1万円は超えると思います。
何で高いのかと言うと、絵の具の元になる顔料(色のついている粉)が高価なんです。

基本色以外もありますが、オススメの色
・フレンチウルトラマリン(マツダスーパー)絶品!
・コバルトグリーンペール(マツダスーパー)
・ブルーコンポーゼNo2(マツダスーパー)
・スーパールビー(マツダスーパー)
・コバルトバイオレット(マツダスーパー)絶品!
・カドミウムグリーンペール(マツダスーパー)絶品!
・オキサイドオブクロミウム(マツダスーパー)
・オーロライエロー(マツダスーパー)
・テールヴェルト(マツダスーパー)
・ローアンバー(マツダ専門家用)絶品!
・ヴァーミリオン(マツダ専門家用)
・コバルトターコイズ(ホルベイン)
・コバルトブルー(ホルベイン、ヴェルネ)
・カドミウムレッドミドル(クサカベ)絶品!
僕は基本的に油絵具はマツダスーパー派で、カドミウムレッド系はクサカベを使っています。

この二つのメーカーは、ラベルの脇に使用している顔料の名称が書いてある、というところがポイントです。色の名前には様々なものが付けられていますが、使用している顔料はある程度限られています。ラベルをよく見ると、違う色の名前なのに同じ顔料を使っているものが多く存在しているのが分かります。
色数は沢山使っているのに、画面全体が似たような色になってしまうという人は、ラベルの脇をよく見て買いましょう。特に?チントとか、パーマネント?という名前が使われている絵の具は、数色の顔料を混ぜて作られた色です。
絵の具を購入する時、参考にしてもらえたら幸いです。