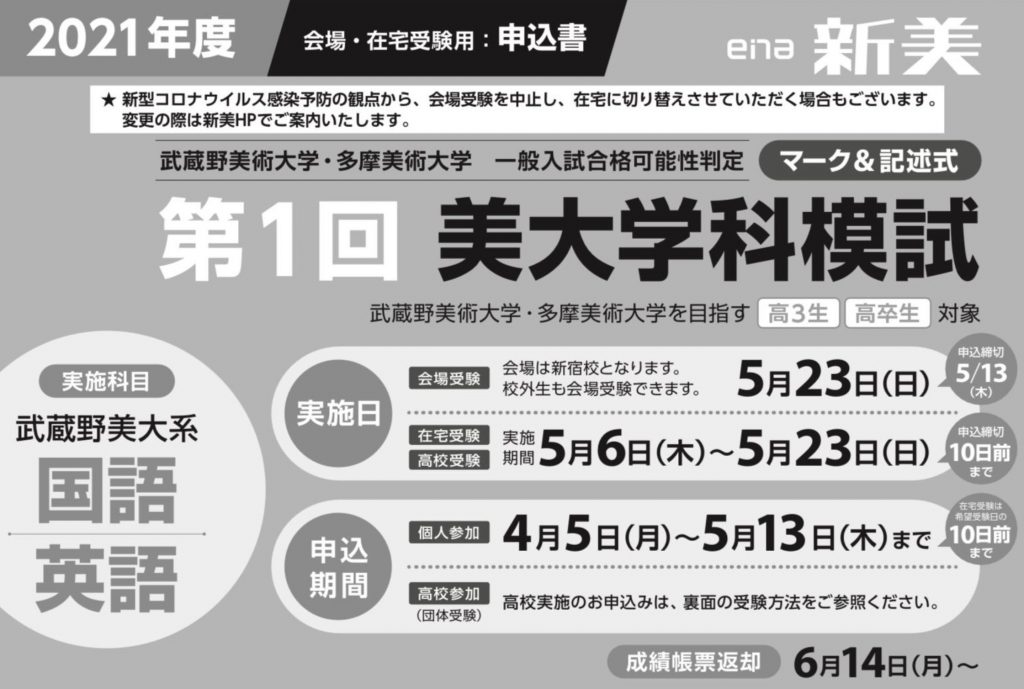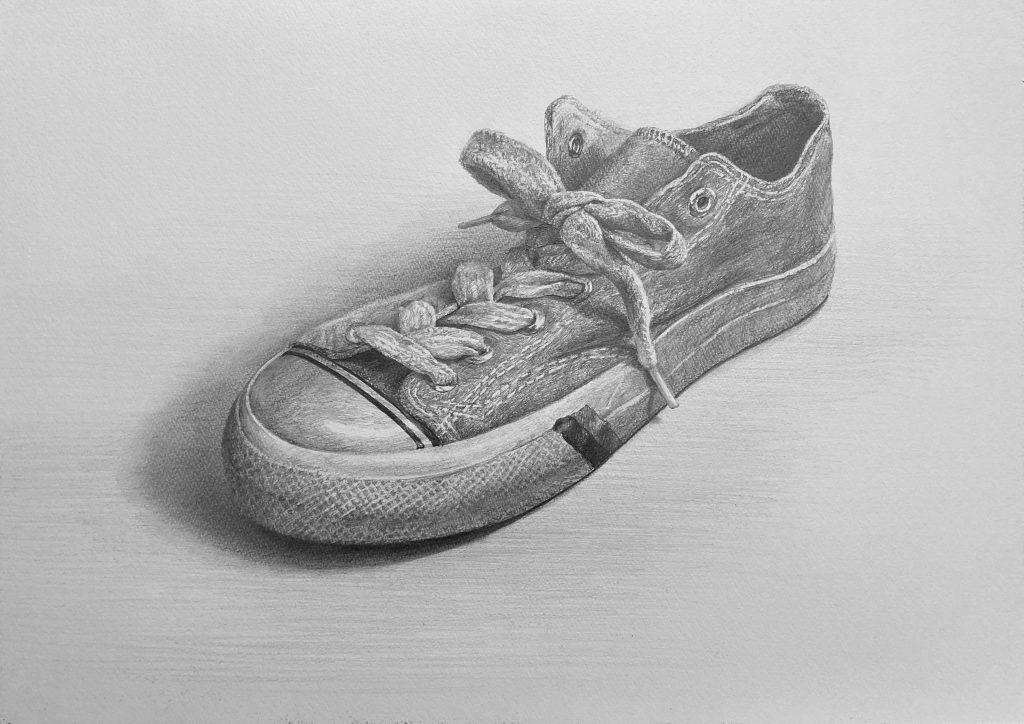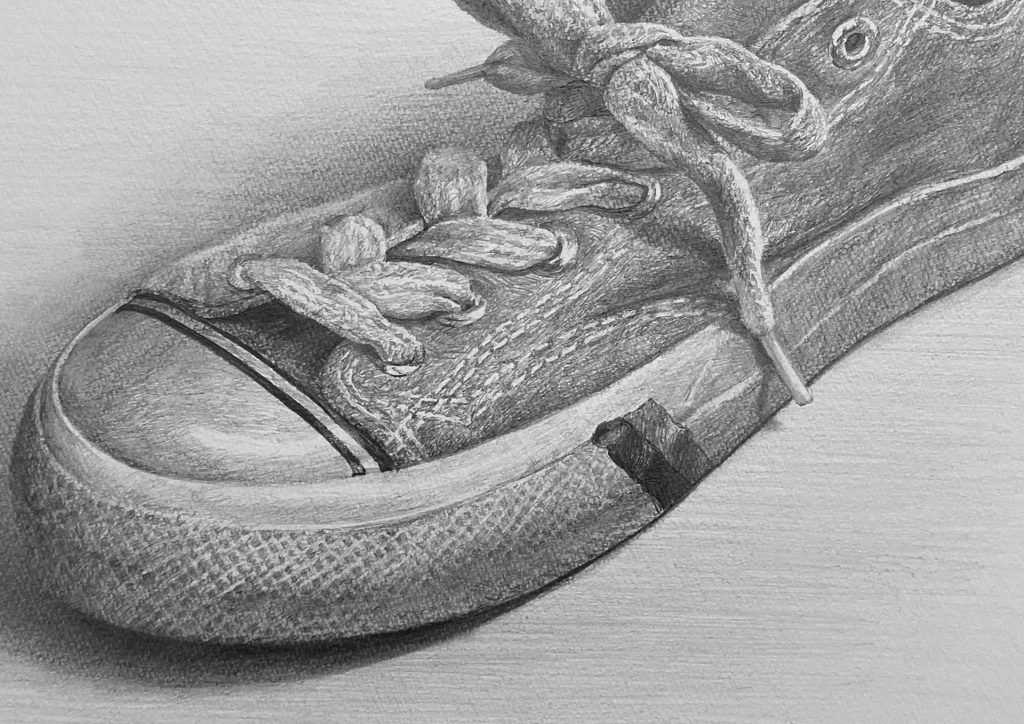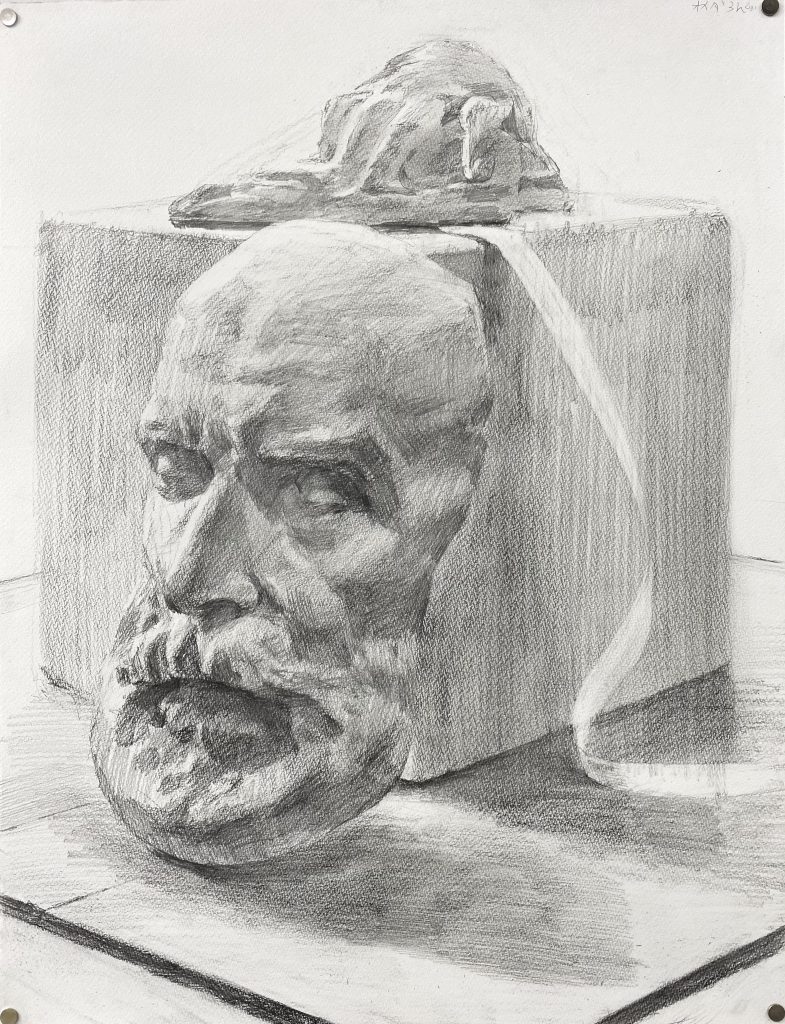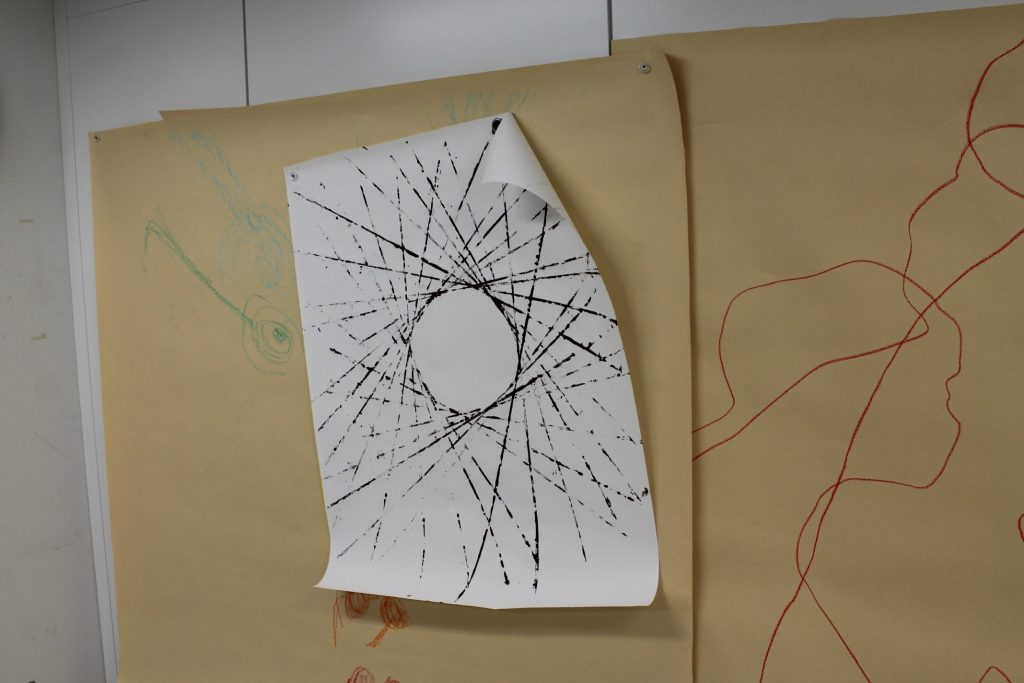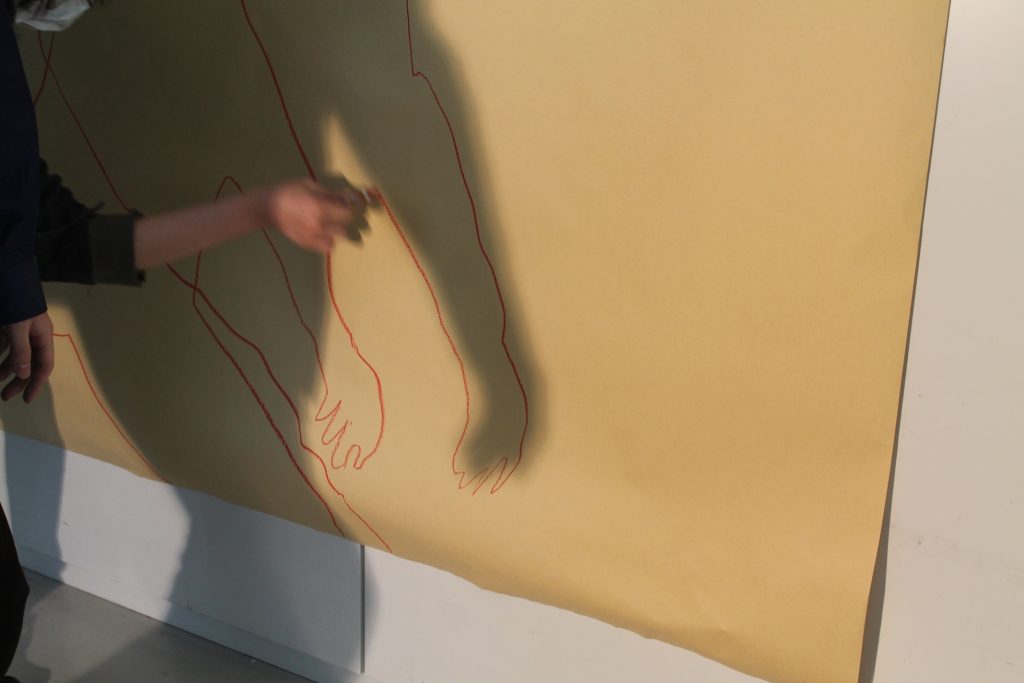こんにちは。
せっかくのGWなのに美術館や展覧会は観に行けない状況になってしまいましたね。
そこで今回はお家で出来る
美術史について勉強してみてはいかがでしょうか?
まず、美術史ですが
歴史嫌だなーー…。と思う方もいるかもしれません。
しかし、美術史とは、ピラミッドが作られていたような古代から現代までの美術の歴史です。
芸術家が過去から学び、新しいことに挑戦して1つ1つの作品が生み出し進歩していく壮大な物語です。
過去から学ぶというのは、過去に作られてきた作品や、師匠から、伝統的な表現方法やテクニックを学ぶこと。
美術史を知ると、歴史は常に先に先に進んでいるのではなく、過去の時代への立ち戻りというのか、流行が戻ってきたというべきか、戻ったり、進んだりして現代まで続いてきていることがわかります。
例えばルネサンスは、中世のキリスト教中心の世界から、関心が人間へ現実世界へと変わっていったので、古代ギリシアやローマの生き生きとした人間表現などの研究が進みます。
そして、新しいことに挑戦というのは、芸術家は自分のオリジナリティーを発揮するために、過去の作品に対し少しでも差を出そうと挑戦し続けてきているということです。
もうちょっと身近なところで
例えばファッションは分かりやすいです。
流行は毎年変わるけど、過去流行ったものがまた舞い戻ってくることよくありますよね?
また、フリースをUNIQLOが販売した。最初は色もデザインもワンパターンだったけど、その後少しづつ改良されていって、他社も差別化を図り商品を作り出しどんどん進化していった。
もう私たちの周りには当たり前のように定着した商品になってますよね。
美術の歴史もこんな感じに進歩してきたのです。
でもそれは過去の作品が劣っているとか、現代の作品が優れているとかいうことではないのです。
美術史の大切さがわかっていただけましたか?
そこで最初から難しい本を読んでも頭にまーったくはいってきません。
なので最初お勧めしたいのはこちらです。
1
巨匠に教わる絵画の見かた (リトルキュレーターシリーズ)
早坂 優子
↑最もオーソドックスな美術史入門だとおもいます。
2
『近代美術史テキスト―印象派からポスト・ヘタうま・イラストレーションまで―』
中ザワヒデキ
↑こちらは全て手書きで書かれていて読みやすいです。
↓また同作者の現代美術 日本編もあります
3
『チャートで読み解く美術史入門』
ナカムラクニオ(著)
↑こちらはイラストも豊富で見ていてもおもしろいです。
このように様々な本が出ているので自分にあった本をさがし以下のようなことを学べるといいと思います。
- 各時代の美術の特徴
- なぜこのような作品が生まれたのか?
- どのように次の時代に移っていったのか?
では残り短いGWを有意義にお過ごし下さい。