こんにちは。油絵科の関口です。
さて、皆さんが絵の道に進むキッカケになったのは何でしょうか? 今日はある田舎で育った少年が、絵の道を目指すまでのお話をしようと思います。
運動音痴で勉強も特に得意な教科が無く、何をやってもパッとしない。引っ込み思案で学校ではイジメにあう事も…でも絵は小さい時から好きで、友達から時々「上手いね」と褒められ、美術の成績だけは良かった。
あなたは小さい時そんな子ではありませんでしたか?
勿論そんな人ばかりではないと思いますが・・・僕は正しくそんな子でした。
僕は3月生まれで、同じ学年の4月生まれの子とは一年近く離れていたので、幼少の頃は体力的にも、学力的にも大きく劣っていたと思います。(学力的に劣っていたのは、単なる努力不足ですが…)小さい時は泣き虫でコンプレックスの塊だったと記憶しています。

ところで、ここスゴい田舎でしょ?
僕は新潟県十日町市出身。こんな豊かな自然の中で育ちました。
実際にウチの田舎に行った人は「関口君の絵のまんまだったね。意外と写実だったんだ(笑)」とよく言われます。
でも心象風景なので、実際は何も見ないで描いています。写実ではありません。
そんな僕が幼稚園の時、描いた絵を先生から褒められて嬉しかった事は、今でもハッキリ覚えています。僕は黒い模造紙の上に糊を塗り、ススキの穂を貼り付けてウサギの絵を描いたのです。
「ウサギさんね。フワフワですごいじゃな?い。」僕が絵に興味を持ち始めたのは、幼稚園の先生の、あの一言からだったと記憶しています。余程嬉しかったのでしょう。それ以来、絵の事が好きになり、暇さえあれば一人で絵を描いていました。
その後、僕は小中高とずっと美術部に所属して絵を描いていましたが、今から考えると特に絵が上手だったとは思いません。同じ学年の仲の良い友達の方が、ずっと絵は上手でした。ただ純粋に絵が好きなだけの「どこにでもいる様な少年」だったのです。・・・まぁ今だって「どこにでもいる様なオッサン」ですが(笑)。
さて、僕が本格的に美術の道に進もうと思ったのは、高校1年の頃でした。当時3年生の美術部・部長の近藤先輩という人が美大を目指しており、彼が放課後に美術室で石膏デッサンをやっていたのを見て、美大という存在を初めて知りました。
その先輩は、デッサンが抜群に上手く、当時の僕にとって雲の上の存在でした。油絵に関しても、東京の予備校(そこはもう存在しませんが)へ講習会に行って、何やら見た事もない得体の知れない液体や粉を使い、時々50号くらいの大きなキャンバスに、豚の胎児など不思議な絵を描いていました。彼はシャイなところもあったので、あまり多くは喋りませんでしたが、僕はその先輩の黙々と絵を描く姿勢に多大な影響を受けたような気がします。
彼は見事に現役で東京造形大学に合格。(その後は交流が途絶えてしまったので、今はどうしているかは分かりません)
「よし、そういう進路があるなら、僕も美大を目指してみよう」
美大がどんなところかも(芸大に至っては存在すら)知らない田舎者の僕は、先輩の背中を見て美術の道へスタートを切ったのです。
ーつづくー




 広岡茂樹「げんまん」 紙、紙粘土、アクリル
広岡茂樹「げんまん」 紙、紙粘土、アクリル GalleryARK(ギャラリーア-ク)
GalleryARK(ギャラリーア-ク)

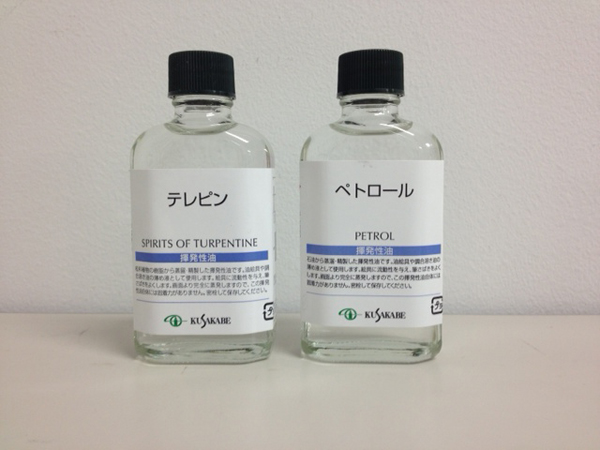


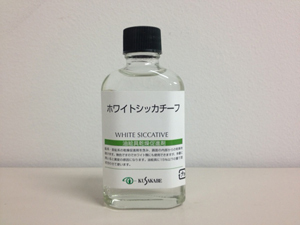 ?・シッカチーフ
?・シッカチーフ
