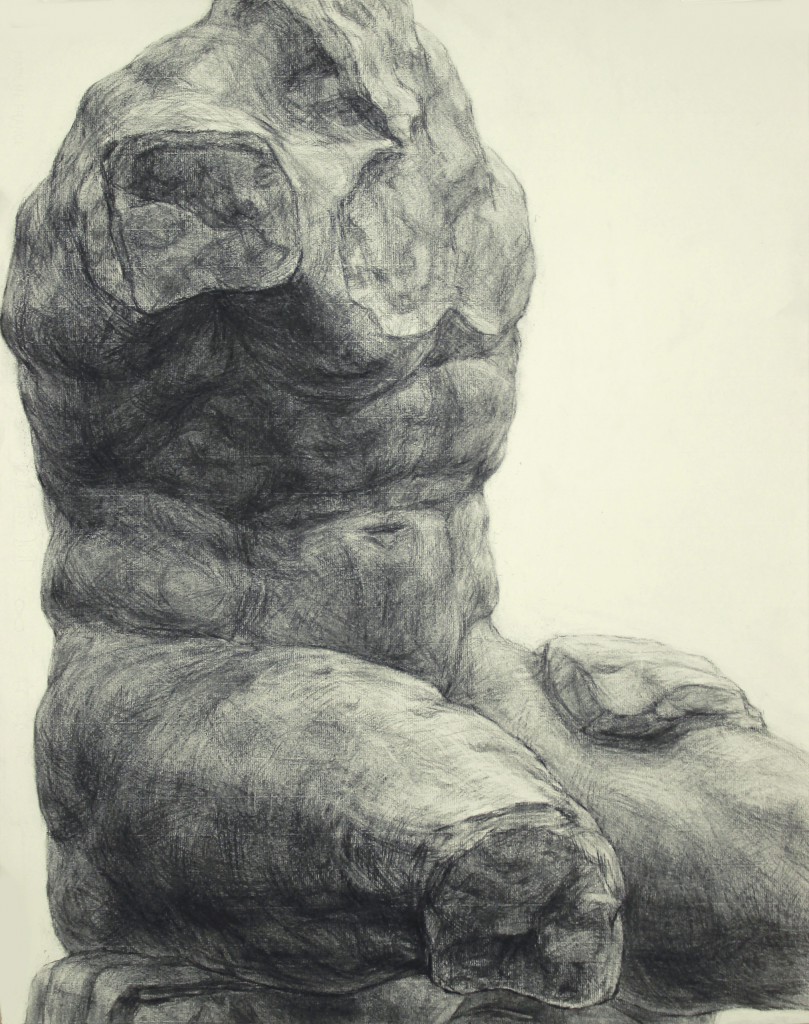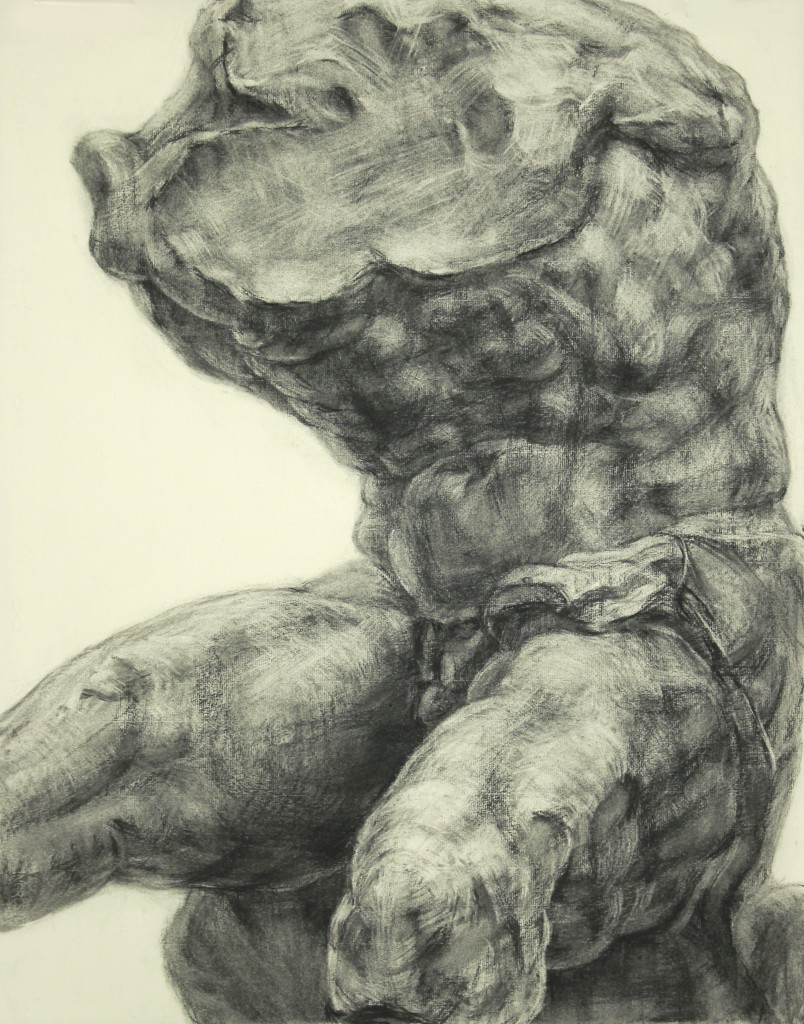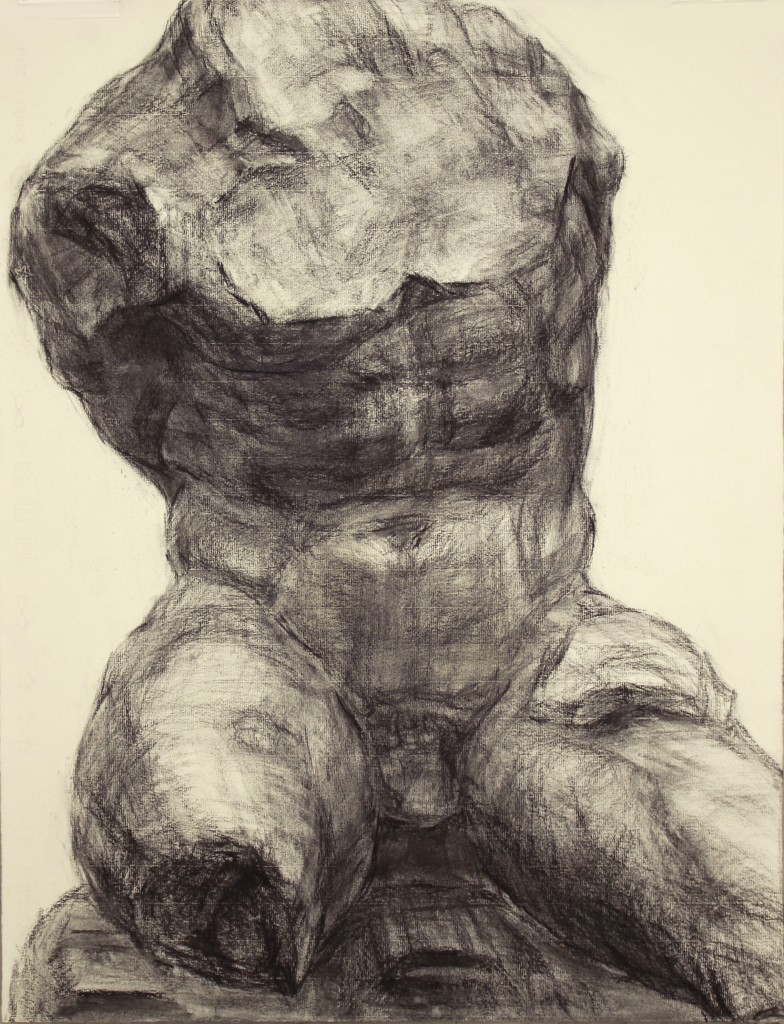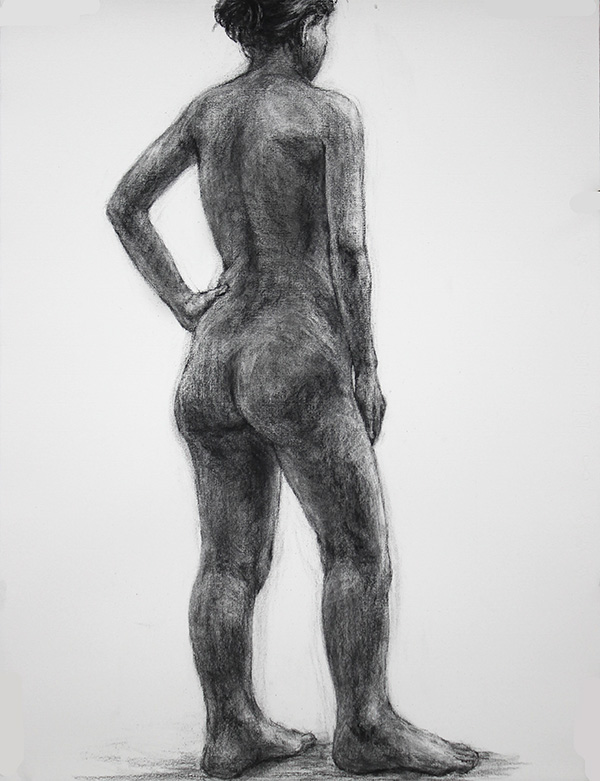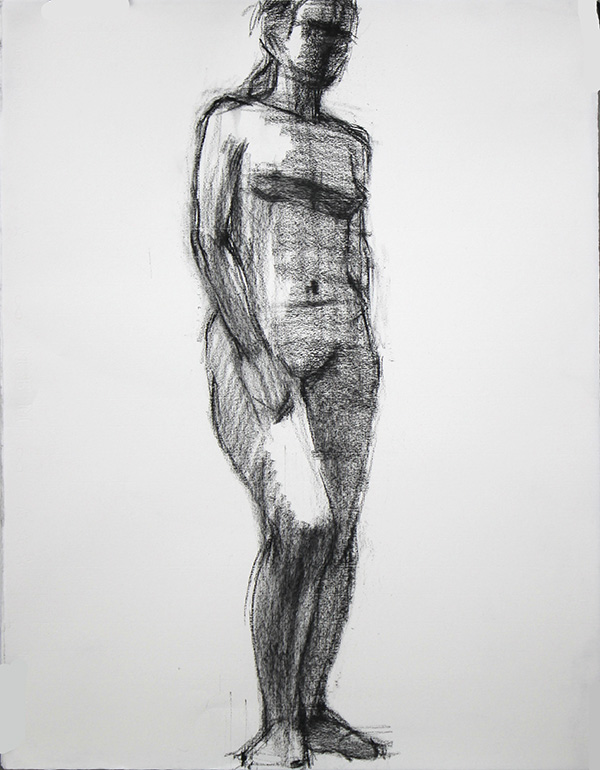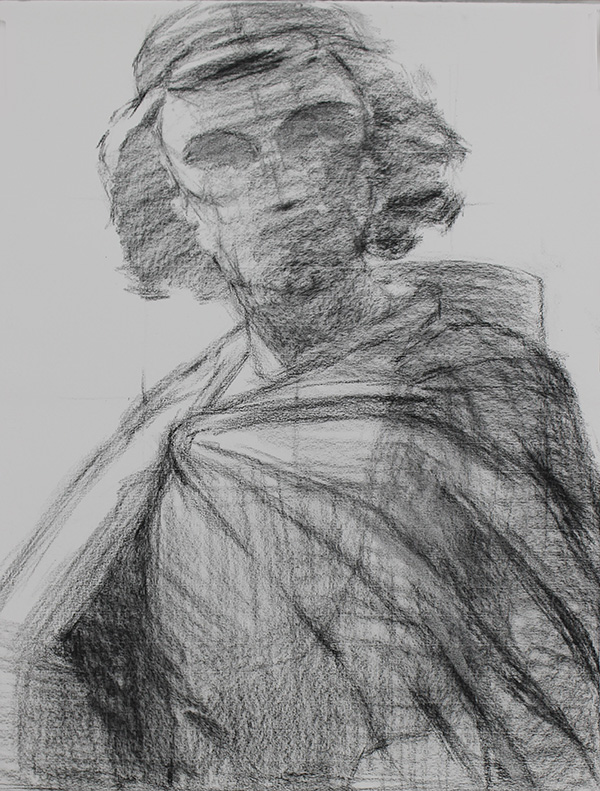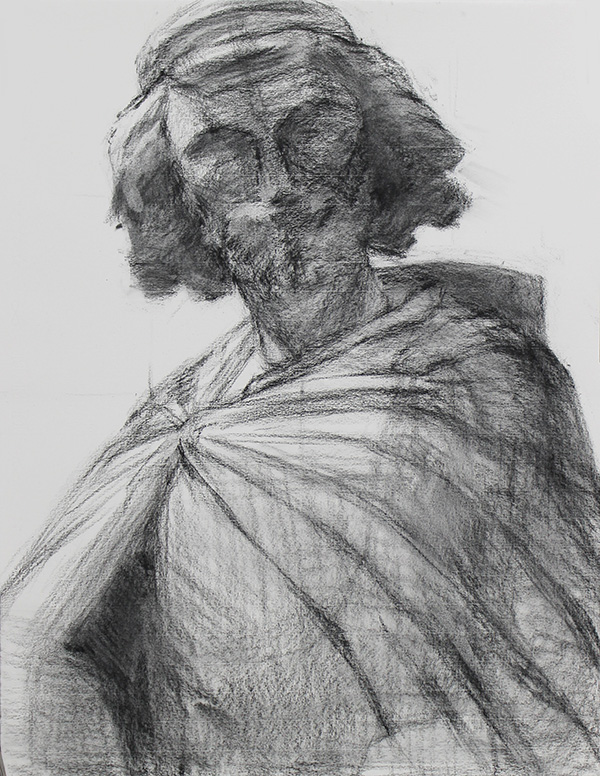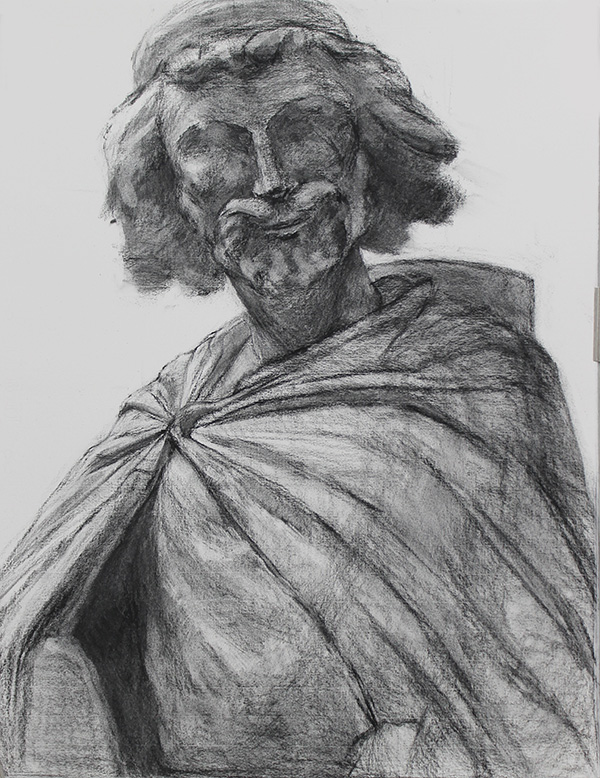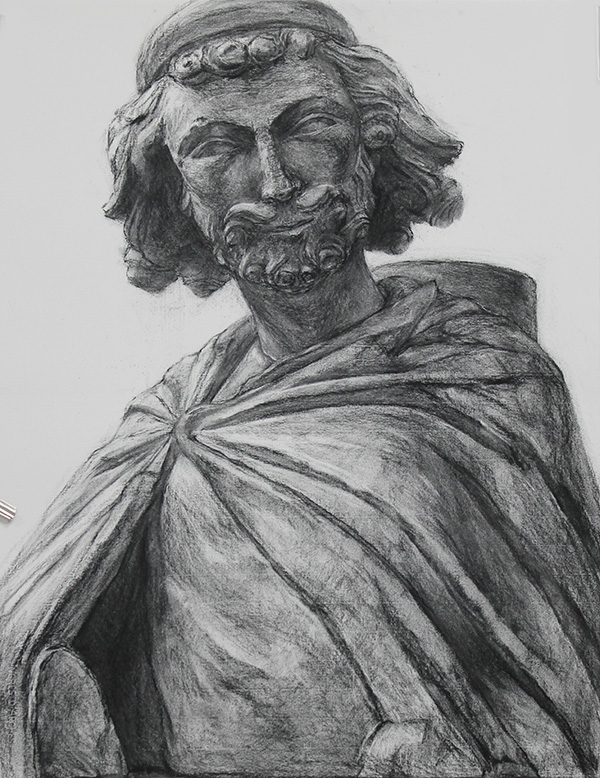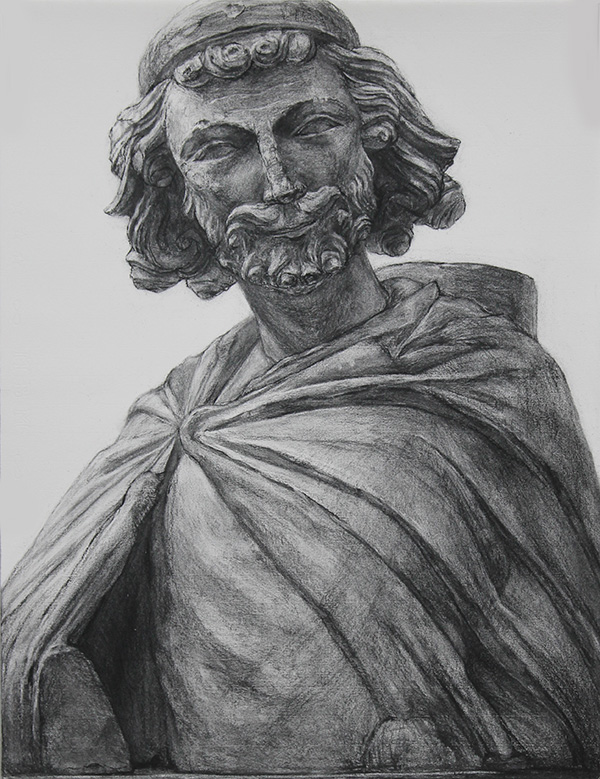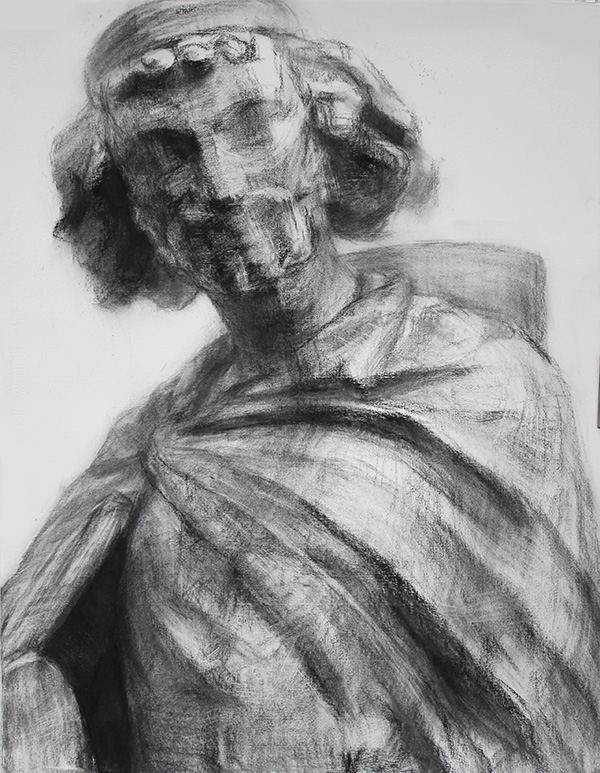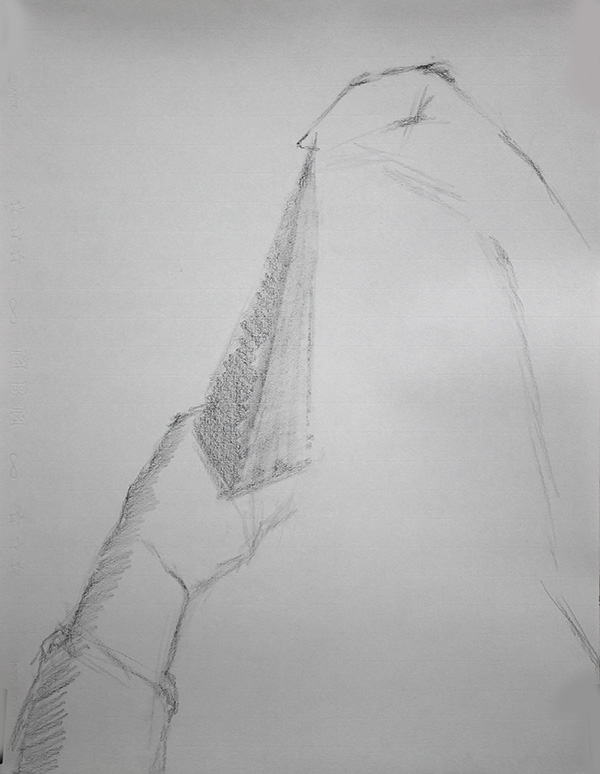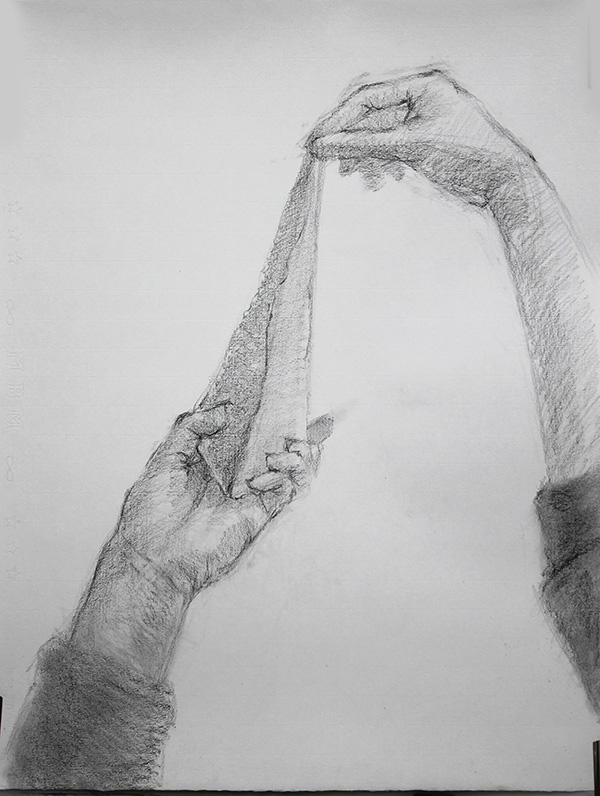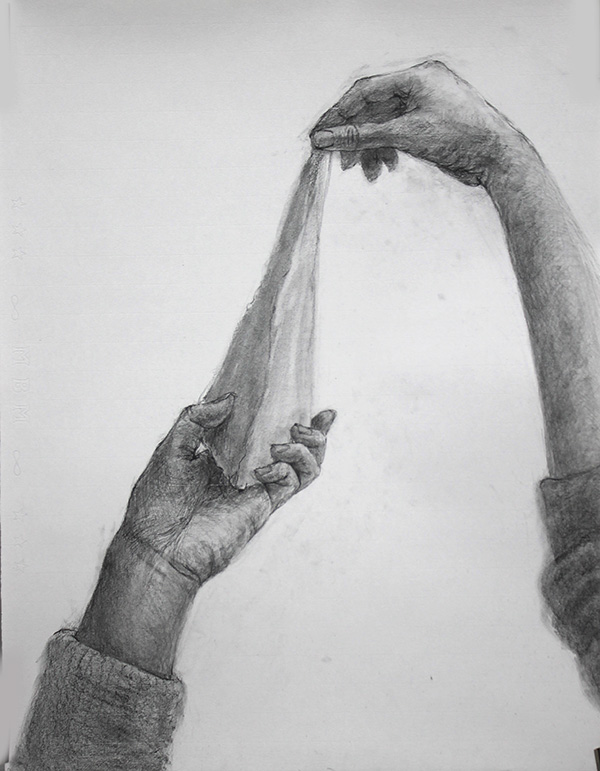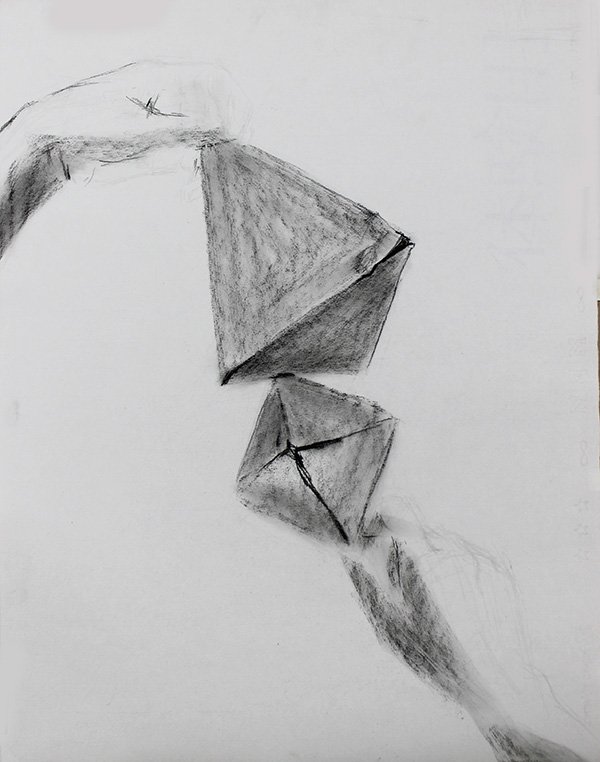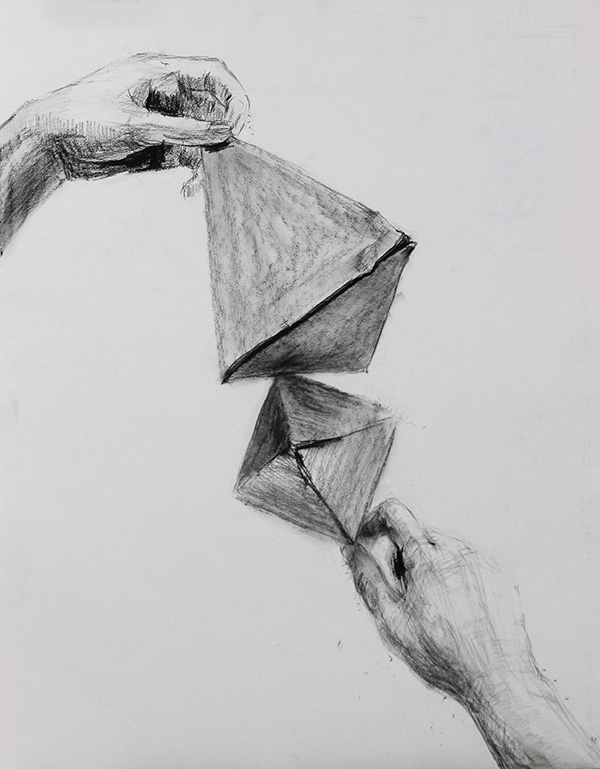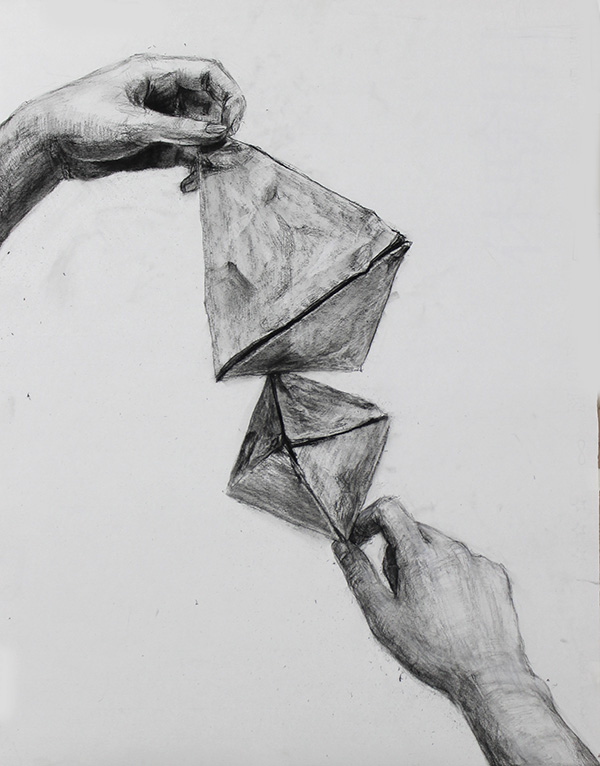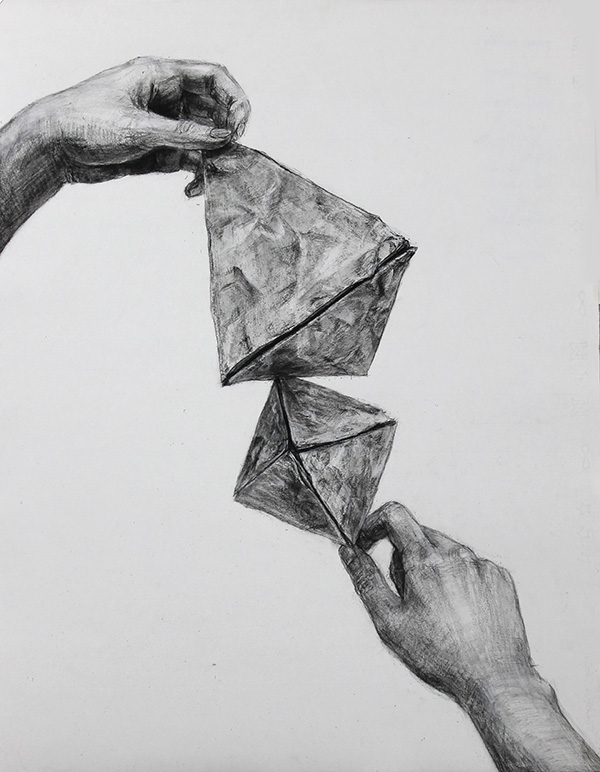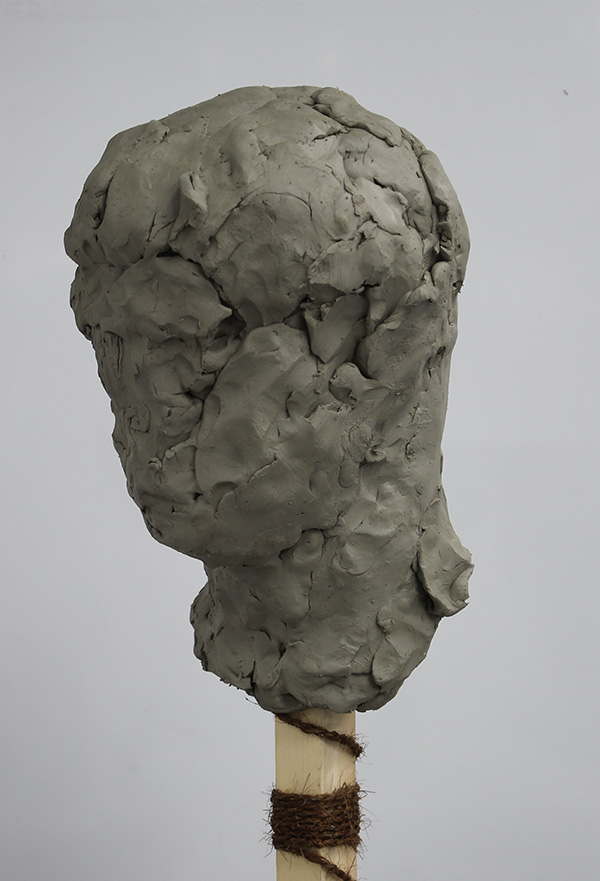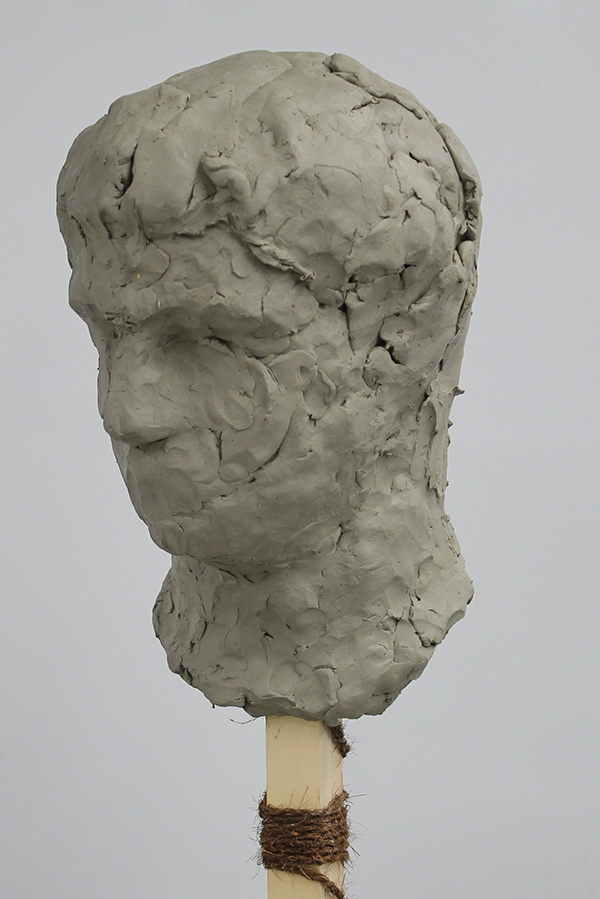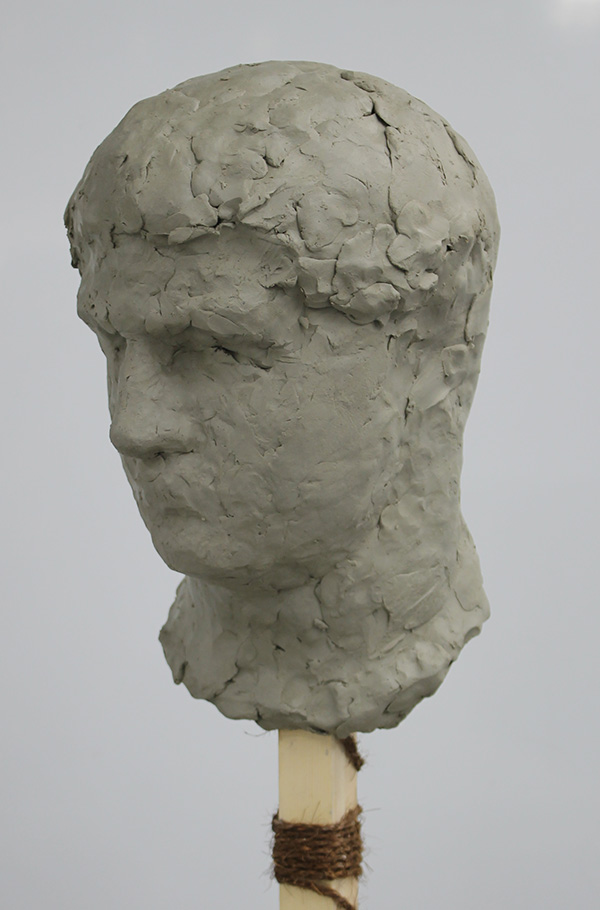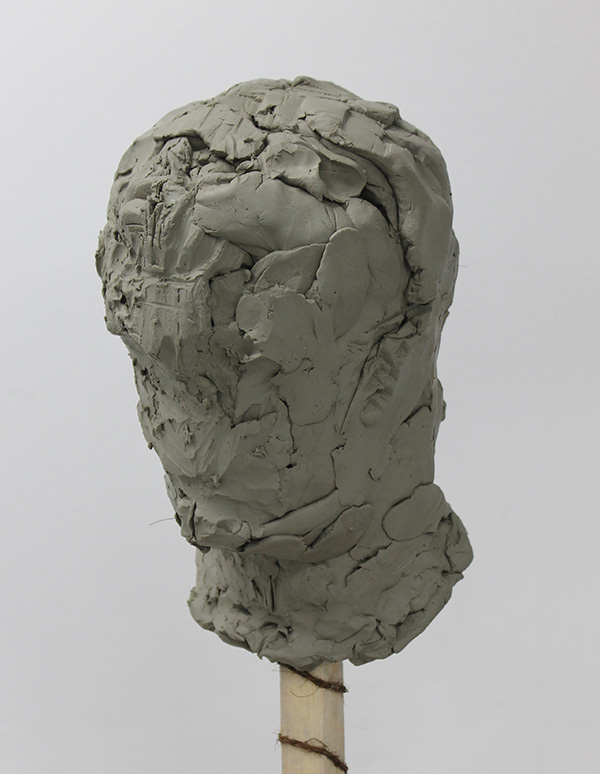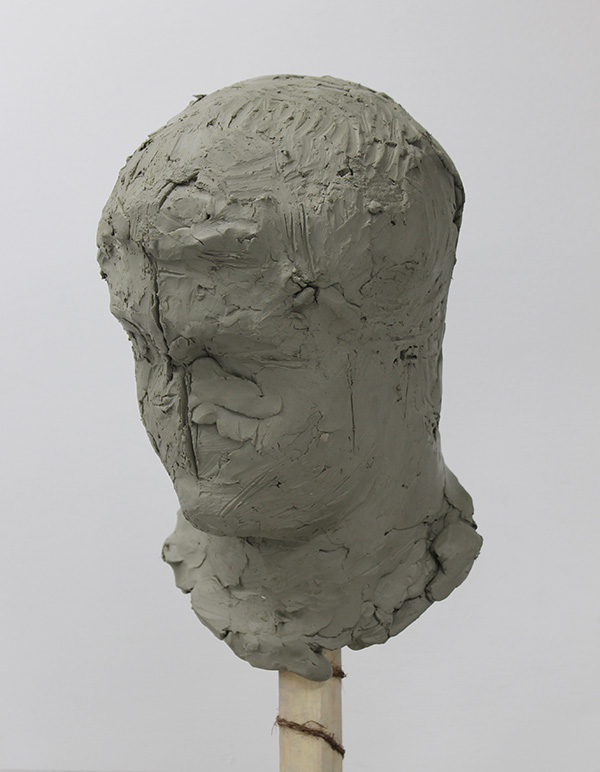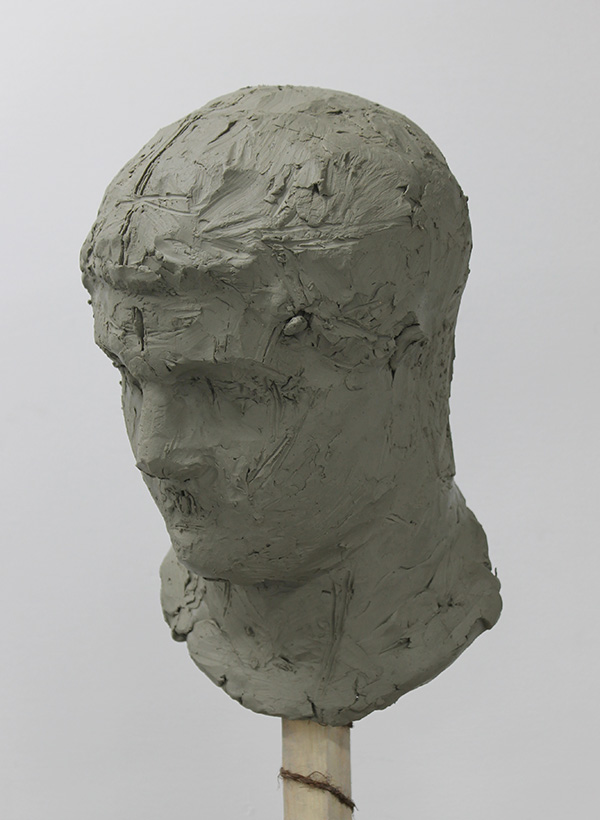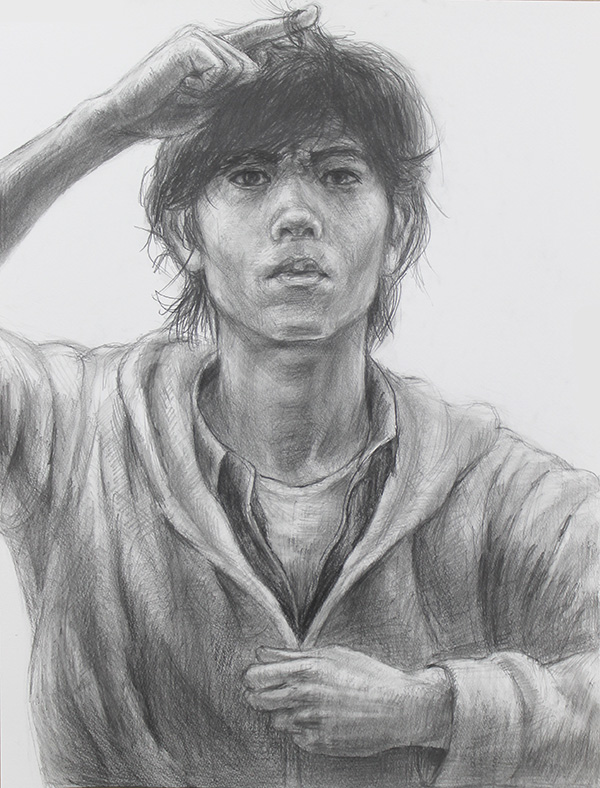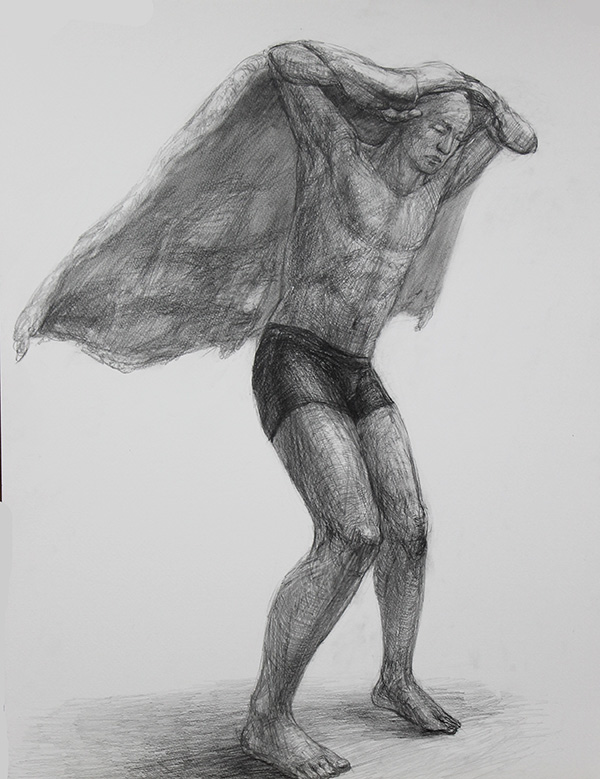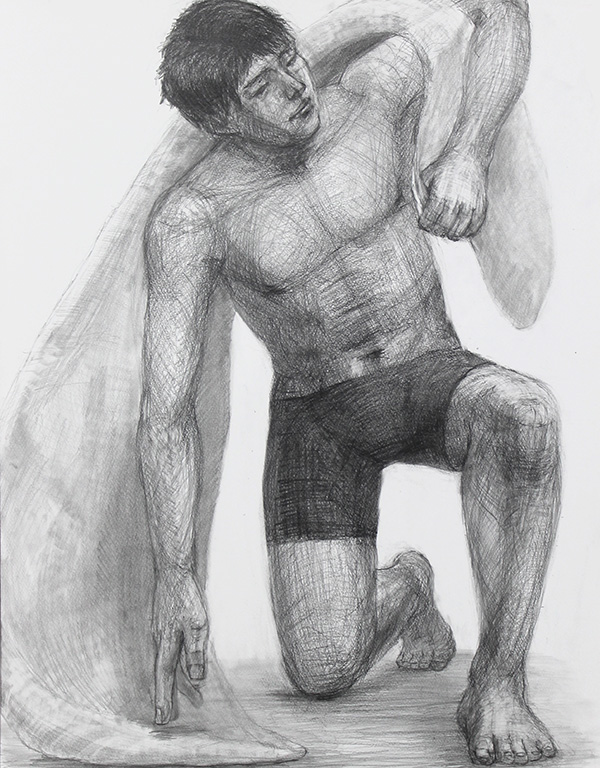こんにちは。彫刻科の小川原です。新学期が始まりました!目標を持って着実に実力を高めていきましょう!
さて、今日は僕が普段制作に使っている道具について紹介します。今後僕の制作の進展状況を載せていく予定ですが、どんな道具を使って作業しているのか知っているとまた見方も変わるのかなと思います。
僕は現在木彫を専門に制作をしていますので、主には木彫用の鑿や彫刻刀を使用します。
一部ですがこんな感じです。

種類は多ければ多いほど作業がはかどります。場所ごとに適した鑿を選んでいくと必然的に数は増えていきます。鑿は研いで使い続けるので一生ものと思えばそんなに高い買い物ではないと(自分は 笑)思います。
下の写真左の二本はタタキノミといって基本ハンマーで叩き込みながら使う鑿です。その隣のは彫刻刀です。これは叩いて使うのには適していません(場合によってはゴムハンマーで叩きます)。細かな作業に使います。そして右のものはちょっと変わった形をしていますが、これは僕が改造した鑿です。どうやって使うものかと言うと…。

元々瓦を割ったり、コンクリートを削ったりする建材加工の為の道具としてエアーを動力としたチッパーと言うものがあるのですが、これを石彫で使うことは一般的です。それを木彫に応用する為にチッパーの軸と鑿の刃先をカットして溶接したわけです。
↓下がチッパーです。右端にエアーのホースをつなぎます。レバーを握ると高速で鑿が打撃運動を連続します。チッパーにも種類があって、僕は1分間に5000回の打撃が出来るものと、20000回出来るものを持っています。

つくり方はこうです。
まずはチッパーの軸と鑿の軸を高速カッターで切って繋げたときにちょうどいい長さにします。鑿は刃物屋さんに注文する時に柄はいらないと言っておくとちょっと安いです。柄の中はこんな軸が入っています。


次に早速溶接ですが、ズレないようにバイスクリップ(固定できるペンチみたいなやつです)で固定しておきます。

軸の中心まで溶け込ませる為に電圧は高めにします。溶接にもいろいろ種類がありますが、これはアーク溶接といいって一番オーソドックスな溶接法です。放電する熱によって金属を溶かしながら同時に溶接棒を溶かし込んでいきます。下の写真では棒を持っていますが、この棒がだんだん溶けてなくなっていきます。

溶接面は必須です。これをしないと失明します!あと、火花が危険なので半袖で作業するのは絶対にやめましょう!光は強力な紫外線なので日焼け必至です(笑)

溶接直後はこんな感じです。

これで冷めれば完成!!
ではありません…。鉄は高温で熱して急冷すると非常にカタくなる性質があります。今この鑿は3000度で熱せられた直後に25℃の常温で急冷されている状態。つまり焼きが入ってしまっています。焼きが入ると対衝撃性が弱まり、折れやすくなってしまうので、このあとこの部分を柔らかく(といってもカタいはカタいです)戻す必要があります。
そこで使うのがガス溶接機と言うものです。アセチレンと言う可燃性のガスを酸素で火力を高めた溶接機です。この溶接機では火力と酸素の勢いを使って分厚い鉄板を切断する(溶かし切る)ことも出来ます。この機器を使って溶接部を再度熱し、冷まし、熱し、冷ましを徐々に温度を下げながら繰り返します。すると分子の結合が緩くなり、めでたく折れにくい鑿が出来るのです。

小豆色くらいの温度帯?赤みが消える温度を繰り返します。

冷めた後ボコボコしてる部分はグラインダーで削ります。これで完成!
ただ、当然ですが使っているといずれ金属疲労でまた折れます。折れてくっつけてを繰り返して骨折が治るように元の太さより段々太くなっていきます。
ちなみに。
コンプレッサーはエアーツールを使うには200Vでないと十分な空気量を得られないですが、僕は100vのコンプレッサーを2台から(↓両端のもの)サブタンクにエアーを集めてそこから引いています。これでエアーが途切れることはありません!

このチッパーは一気に量を落としたいときに使います。手仕事より早いです!でも微妙なコントロールは出来ないので、形を決める作業は当然手仕事でないと出来ません。適材適所っていう感じですね!
あんなこといいな!できたらいいな!ってことは自分で開発する。彫刻は、新しいことをやろうと思ったら常に技術的に壁にぶつかるので、それをどう乗り越えていくかと言うのは割と日常的なことかもしれません。