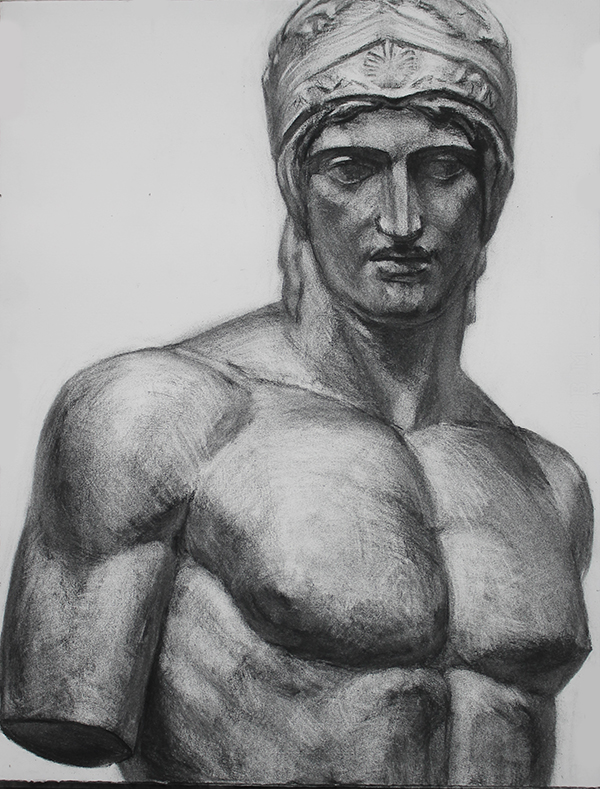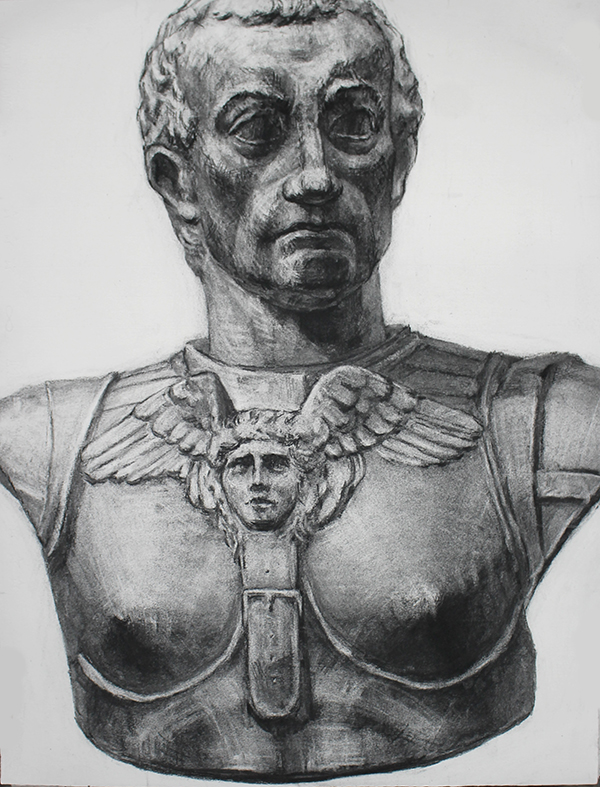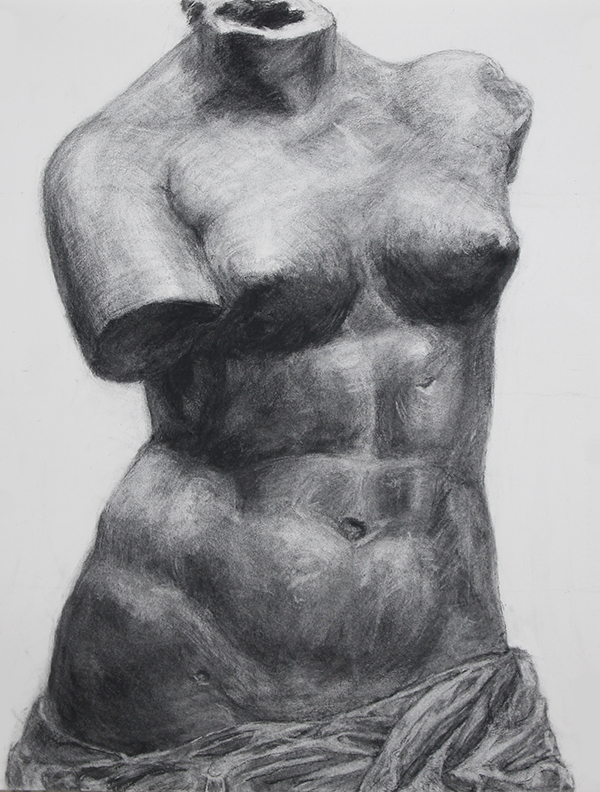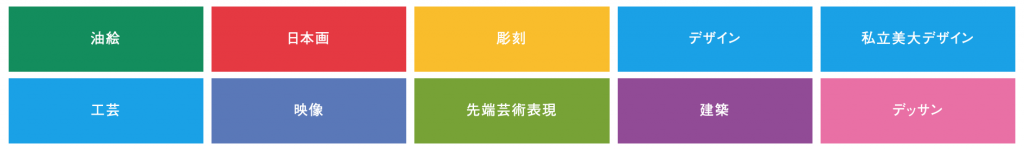こんにちは油絵科昼間部です。
夏期講習が終わり2学期が始まりましたね。
夏期講習で初めて新美に来た方は新宿駅の複雑さに戸惑った人も多いと思います。
新宿駅は最近東西連絡通路ができ大変便利になりましたが、初めて利用する方は苦労する駅です。確か利用者世界一でギネス記録に載っていたはずです。私も新美に通い初めの頃は毎日迷って迷宮探索していた記憶が有ります。だんだん慣れて好みのルートができてくるのですが、同じ目的地でも人によって道順に違いがあり面白いです。地下から行くか地上から攻めるか、、、、

写真は昔新宿駅の地下で行っていた、新宿駅の模型の展示写真です。再開発が絶えず進められていますので現在の状況はまた違うのですが、こうしてみると広範囲への広がりと共に立体的な入り組みが合わさってできてい流ことがわかります。普段はただ歩いているだけですがこうして視点を変えると視覚的なインパクトが全然違って面白いですね。少々強引ですが観察する視点というのは自身の目を通したものだけでなく俯瞰的な視点や想定的な視点など、多くのものの見方があると思います。地学や化学などいろいろな図式がありますがそういったものには目的に応じた視点が設定されていているので見るだけでも結構楽しむことができます。


 日時 9/12(日)13:30〜17:30
日時 9/12(日)13:30〜17:30