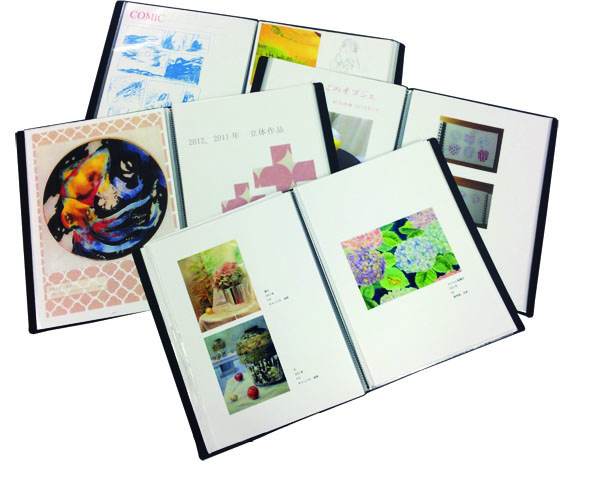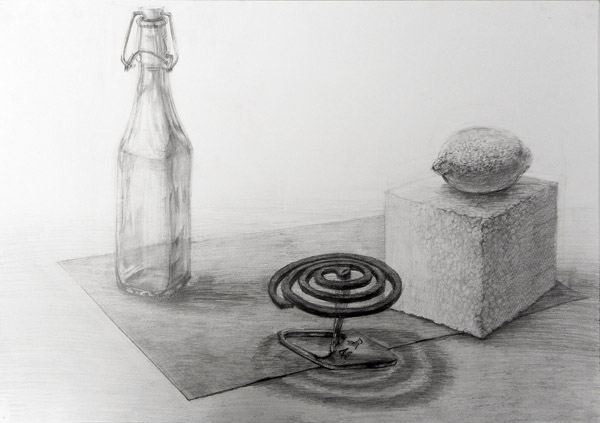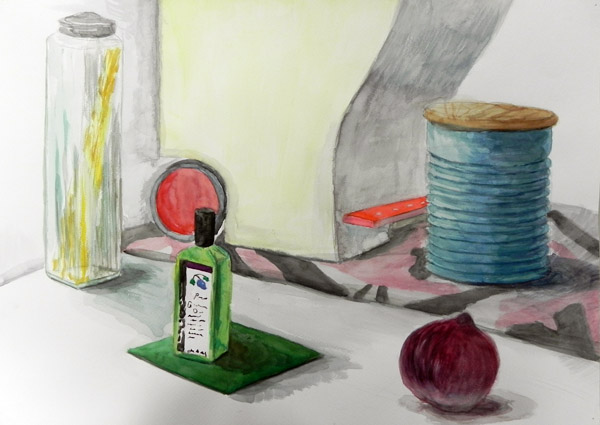こんにちは油絵科の関口です。
今回はオイルについてお話します。中でも皆さんもよく使うテレピン油についてです。前回オイルについてお話したのは12月になりますので、興味のある方はこちらを参照して下さい。
オイル(画用液)について①
http://www.art-shinbi.com/blog/20141215/
オイル(画用液)について② ?カテゴリー編
http://www.art-shinbi.com/blog/20141222/
テレピンは、オイルのカテゴリーでは「揮発性油」というジャンルになります。揮発性油というのは、読んで字のごとく揮発する油です。お皿とか浅い容れ物に入れておくと、時間の経過と共に大気中に揮発してしまうので、放って置くと無くなります。水彩で例えるなら、水みたいなものだと思って下さい。

用途は幾つかあります。
①絵の具の濃度や粘度を薄めたり、他のオイルを希釈する。
②乾きが早いので、描き出しの時に全体を捉えるのに使う。
③溶解力が高いので、ダンマル等の樹脂を溶かして樹脂溶液を作ったり、溶かす力を利用して、描いた絵の具を拭き取ったりするのに使う。(実は筆に溜まった絵の具もテレピンで洗うとかなり落ちます)
これらの理由で、結構便利なオイルですが、単独で使うのは描き出しのみに留めておかなくてはいけません。何故ならテレピンは固着力が無く、単独で描くと画面に定着し辛いのです。
揮発性油には、他にもペトロール(別名ミネラルスピリット、ホワイトスピリットとも言う。石油系でテレピンより若干乾きが遅い)とスパイクラベンダーオイル(別名アスピックオイルとも言う。植物系で揮発性油の中では一番乾きが遅い)があります。
テレピンはこの揮発性油の中では一番揮発が早く、早く乾きます。
あと、テレピンの主成分であるαピネンというオイルがホルベインとクサカベから出ていますが、テレピンより若干乾きが早いみたいです。少しでも乾きを早くしたいという人は使ってみる価値があるかもしれません。

テレピンは結構サラサラしているオイルです。匂いは独特で、程良い刺激臭。好きな人には堪らないものですが、油絵科でこの匂いが嫌いな人は辛いかもしれませんね。
ところで、皆さんの中には画材屋さんや塗料を売っているホームセンター等で「ガムテレピン」なる商品を目にした事があるかもしれません。ガムテレピンとは、精製する前のテレピンの事です(厳密に言うと別物も存在します)。安価ですが、匂いはテレピンと比べると圧倒的に臭いです。僕も学生の頃にガムテレピンを一斗缶で購入し、友達とペットボトルに分けて使っていましたが、樹脂分が残っていて少しベタベタが残り、匂いが強くて服や髪の毛にも匂いが染み付いてしまうので、最近では全く使わなくなりました。
ちなみにホームセンターで売っているガムテレピンには注意が必要です。少しでもテレピンが混ざっていれば、ガムテレピンと表記ができるそうなので、ガムテレピンと表記されていても、テレピンの含有率が少ない粗悪品もあるようです。安いからと言って安易に手を出さないで、ちゃんとしたテレピンを買って下さい。

あと、テレピンを大量に使う人には大瓶で買うのをお勧めしますが、普通の人は中瓶、ほんのちょっとしか使わない人は小瓶をお勧めします。何故かというと、空気と触れると酸化して行くので、時間の経過で少しずつ劣化して行きます。僕の経験では、数年放置したテレピンを使うと、何日経っても乾かないベタベタな感じになりました。イメージとしては、炭酸飲料をちょっとだけ残しておいたら、数日後には甘くてベタベタものだけが残る感じありますよね?あんな感じです。え?飲んだ事無いから分からない?そういう人はベタベタのテレピンを使う事が無いと思うので大丈夫です(笑)。