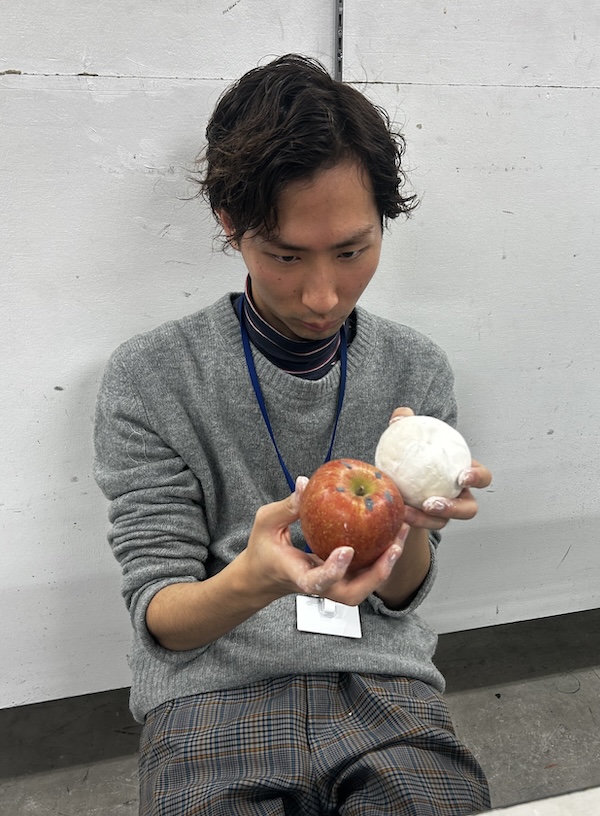人間の心というのは不思議なもので、
土壇場で自分に嘘をつける人はあんまりいないんじゃないでしょうか。
土壇場で「頭真っ白になった」とか「いつもやらないことやっちゃった」とかよく聞きます。
自分が普段どれだけやってきたのかが偽ることなく試されてしまうのが、受験などの本番です。
受験当日落ち着いてできるというのは要は、「これだけやってきたのだから大丈夫」と自分に言い聞かせられるぐらい、この1年を過ごせたか?なのではないかなと思っています。
その時に「いやまだやれた、、、」「あーあそこやっておけばよかったな、、、」
なんてことを思ってしまうと、建物の土台がすこしずつ崩れていってしまい
ガラガラと色々なものがそこから崩れてしまうのではないでしょうか。
(落ち着いて考えればできたこととかもできなかったりするんですよね…)
基礎が大事、とよく言いますが、本当の基礎というのはそこなんではないかと僕は思っています。
どんな問題が来ても揺るがない基礎や土台。
それはやはり数や経験なんではないかなと。
時短や効率化というものがたくさん世の中に増え、とても便利になってく一方で、
身近なうちに身についたスキルや知識は、抜けていくのも早いです。
短時間かつ効率的に身についた技術に対して、絶対大丈夫、と自信を持てたら良いのですが、
やはりそうはいかないのが人間なんではないでしょうか。
世の中の技術の進歩はこの100年でとんでもなく急速に飛躍しましたが、
人間の本質というものはそんなに変わるものではなかったりします。
努力とか根性論ではなく、
自分が自分で信じられるぐらいやってこれたか?
それを自分に問われる瞬間が、受験というその日なのではないでしょうか。
大人になってくると、
試験や受験というものが減ってきます。
そうすると、自分がどれぐらい普段やってきたかという客観的な物差しみたいな
ものがなくなってきます。
意外とそういうものがあったことで、「ああもっとやらないとな」とか
「今回頑張ったな」とかわかったりしてたんだな、と思ったりもするわけです。
今週末、多摩美術大学、武蔵野美術大学の合格発表です。
基礎科にいた生徒さんのほとんどが受験をしていますし、
このまさに今ドキドキしながら発表の日を待っているのではないでしょうか。
皆さんが悔いなくこの1年過ごせて、しっかりその結果がついてきていることを
基礎科から願っています。

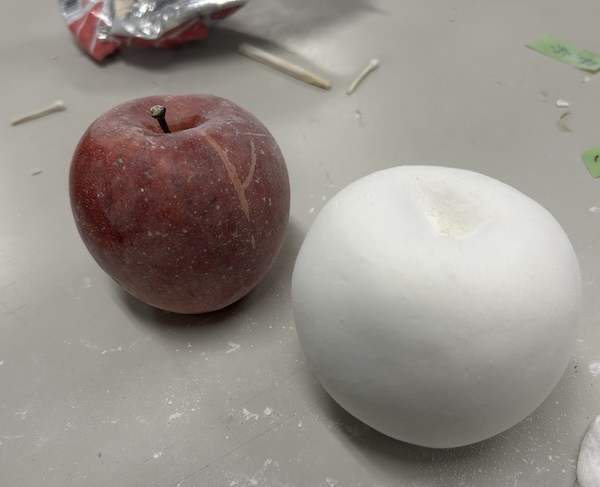


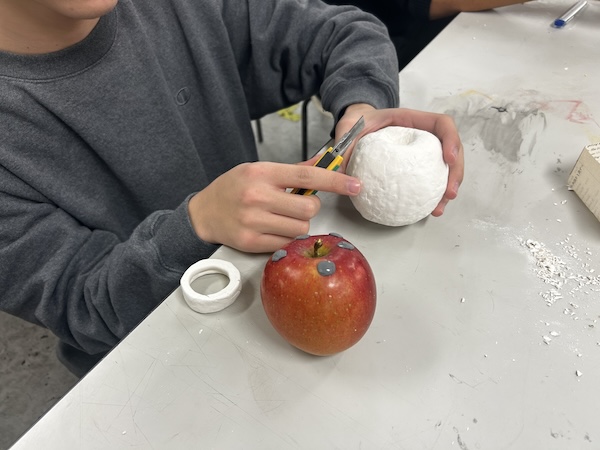 基礎科は今年から参加された先生が多いので、
基礎科は今年から参加された先生が多いので、