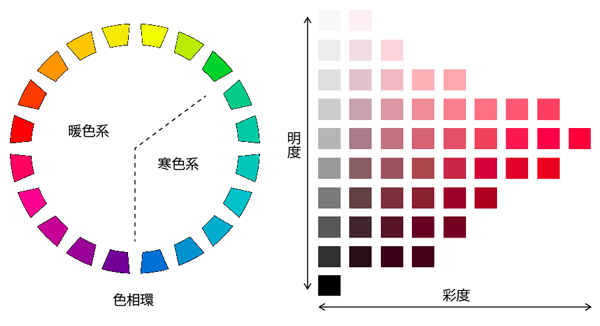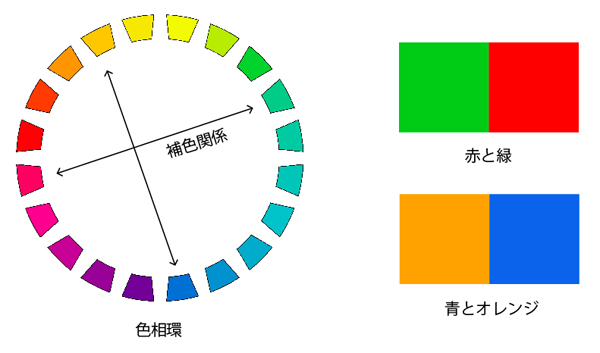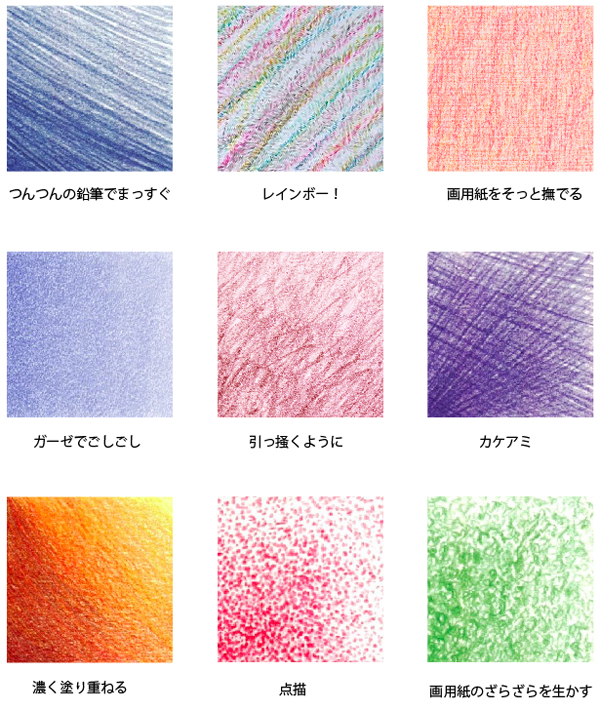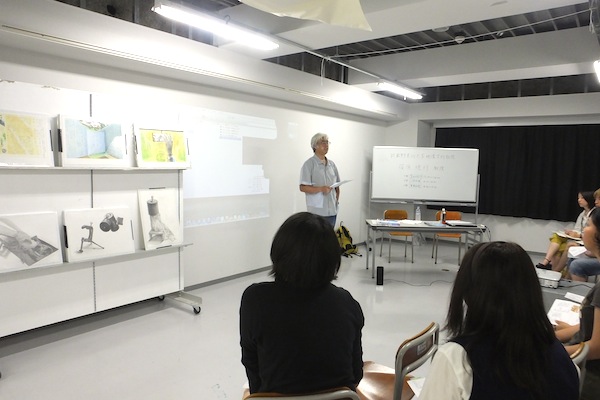こんにちは、映像科の森田です。直前のお知らせということになってしまいますが(というかこの記事をアップする金曜日が申し込みの締切日ではあるのですが)12日・13日は映像科の公開コンクールが開催されます。映像科では毎年武蔵野美大映像学科の模擬試験を行っていますが、今回は受けられないという人のためにも少しコンクールの内容を紹介しておきます。また次回のブログでは公開コンクールの問題を解説しながら、最新の武蔵美映像学科の対策についてもお伝えする予定です。お楽しみに!
■【実技/必須】
○感覚テスト(150点/3時間)…与えられたテーマから創作する問題です。B3画用紙に絵と文章によって表現します。去年のテーマは「近づくにつれて」というキーワードでしたが、さて今年はどうでしょうか。
■【選択科目/小論文と鉛筆デッサンから選択(実際の試験では数学を選択することもできます)】
○小論文(150点/2時間)…工業製品などのモチーフを観察したことをきっかけとして書く内容になってします。
○鉛筆デッサン(150点/3時間)…こちらも工業製品を中心とした基本的な鉛筆デッサンですが。
*なお、ここ数年の過去の出題では、小論文と鉛筆デッサンのモチーフが一部共通することもありました。
■【学科】
○国語・英語(各100点)…今年から出題に変更があることが発表されています。詳しくは武蔵美のWebで見てみてください。
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ところでそんな映像科生やすべての美大受験生におすすめしたいしたいのは、9月27日から東京都現代美術館でやっている『AROUND MICHEL GONDRY’S WORLD ミシェル・ゴンドリーの世界一周』展です。ミシェル・ゴンドリーは元々はミュージック・ビデオの制作で有名だった人ですが、2000年代以降は映画監督としても活躍しています。映像科の授業でも「記憶をビジュアル化している映像作品」のひとつとして初期の映画『エターナル・サンシャイン』を紹介したことがあります。
今回の展覧会はミュージック・ビデオの代表作19作品を見られるインスタレーションと、映画に使われた大道具や小道具、そしてゴンドリーのドローイングなどが展示されていますが、ある意味で展覧会のメインになっているのが、展示会場のセットを使って実際に映画を作ることができるワークショップでしょう。期間中の水・土・日曜日と祝日に行われているらしく、事前に予約すれば誰でも申し込めるようです。そんなこととは知らずに観に行ったのがちょうど水曜日だったのですが、さすがにワークショップの風景は載せられないので、展示されているセットのうちのいくつかだけ撮影してみました。
展示スペースへの入り口はこんな感じ。美術館の中に突如ちょっとレトロなレンタル屋が現れます。

路地裏(?)のセット。グラフィティやブロック塀の汚れもリアルです。

電車に乗っているシーンも撮れちゃいます。写真ではわかりづらいですが、車窓は液晶モニタになっていて、昼/夜、都会/郊外などの操作も可能。

キャンプのシーン。楽しそうですね。

派出所と、奥には取調室的な部屋もあり。

ワークショップがない日もこれらのセットは入ったり写真を撮ったりできます。興味を持った人はぜひ実際に行って見てみてください!(来年の1月4日までやっているようです!)