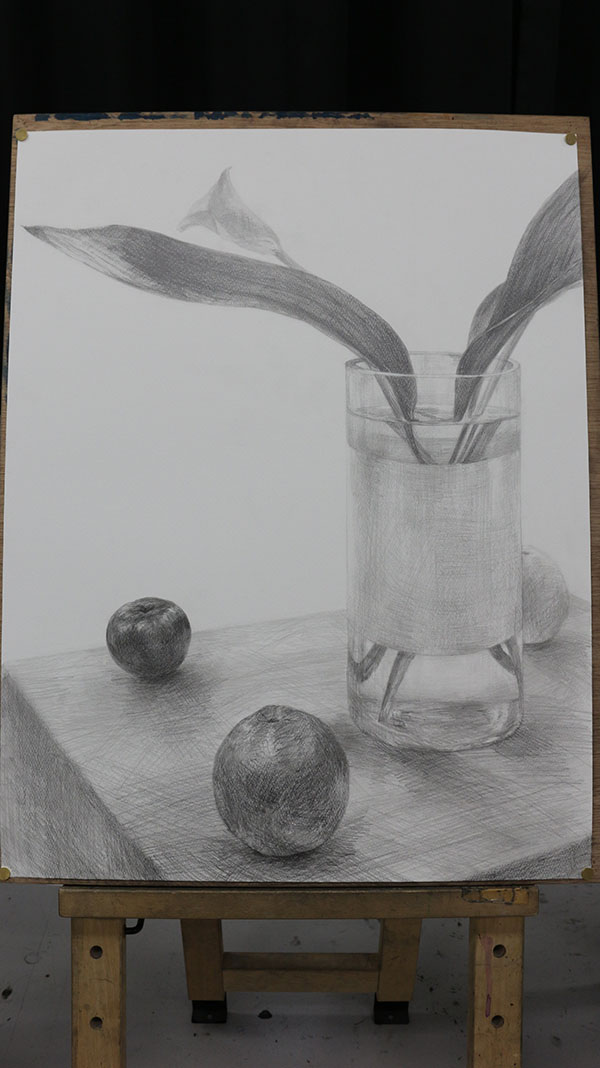こんにちは、映像科講師の土屋です。
映像科では5/7(日)に、先端芸術表現科と合同で
ゴールデンウィーク課題発表会を行いました。
これから「自分が作りたい作品」や「作ってきた作品」、
あるいは「好きな作品や映像に関して各自で研究したこと」について、
プレゼンテーションを行ってもらいました。

先端と合同ということで、生徒のみなさんも
新鮮な気持ちで発表/傾聴できたことを期待します。
さて、ここで講師の私も
気になっている映像表現について発表してみようかと思います。
今回は、
【映像ジャンル研究】「電子音楽のライブにおけるスクリーンの多様性」について。
何故この話かというと、
上記のプレゼンの前の週に「映像ジャンル研究」という授業を行ったのですが、
①『音楽の演奏+(とともに投影される)映像』
②『音楽(DJ)+映像(VJ)』
③『ミュージック・ビデオ』
この3つの違いが分からない…という声を聞いたため。
確かに音楽と映像が絡んだ表現って複雑です。
特に色んな音をシンセやラップトップPCから出して演奏してると…
それは録音されたものなのか、ライブで今演奏してるものなのか?
といった観客にとっての疑問が、映像にも生じてくるのでしょう。
音に対して計算しつくされた映像が出るのか、もっと演奏のようなものなのか。
とはいえ、音楽のある場所にもまた、映像の可能性があるということが
ここに出す例のような表現から感じられるのではないでしょうか。
今回は映像のコンテンツ(内容)から一歩引いて観察してみる、という意味で
スクリーンのバリエーションに注目してみたいと思います。
Radiohead – Live at Tinley Park (2012)
いきなり純粋な意味で電子音楽ではないですね。すいません。
2012年に行っていたステージ演出では
正方形のLED?スクリーンが、それぞれ巧妙に移動して、
さまざまなパターンを作り出していました。
そこに映像が出力されることでまるでミラーのように見えたのです。
+
Squarepusher – 303 Scopem Hard [Live at Hackney Empire, October 2012]
門のような形状が少しずつ奥行きをもったスクリーン。
しかもよく見るとSquarepusherの被っているマスクも映像装置になっているという。
+
Flying Lotus – Live Show Preview (2014)
ティザー動画のため短くて分かりにくいかもしれませんが、
半透明のスクリーンが層になって、Flying Lotusを囲っています。
ライブではなかなか映画館のような3D上映システムは難しいので、
手軽にそんな体験が出来るのではないかと予想。
+
Amon Tobin ‘ISAM’ Live (Trailer) (2011)
プロジェクション・マッピングをいち早くステージ演出に取り入れた好例ではないでしょうか。
最近では’ISAM 2.0’にバージョンアップしているらしい。
以上はスクリーンの形状に注目してみた例ですが、ここで紹介した2012年前後の例は、
「音楽の演奏(=音の電気信号)の出処(=演者)を巧みに隠す、あるいは顕著に見せるための
光/映像の変化」なのではないかと思っています。
ステージにある様々な要素や特殊な造形は、私達を音楽とともに撹乱させます。
しかし趣向を凝らしたステージ演出でも、そこに演者がいなければ、私達観客は観るのを止めてしまうような気がします。
今現在の2017年は
VRやペンライトシステム、3D(ホログラム?)といったテクノロジーが更に発達しているので
観客(私達)と演者の関係がもうすこし複雑な話になってきそうな時代です。
やはり音楽を耳だけでなく、様々な感覚をもって体験したいという欲求なのではないかと思います。
その要素の一つとして、人が集う場所にもたらされる映像(つまり大きなスクリーンが存在する)は演者と私達観客の関係において、効果的に使われているのだと思います。
いかがでしたでしょうか。
映像科の生徒のみなさんはどんな感想を抱くか気になります。