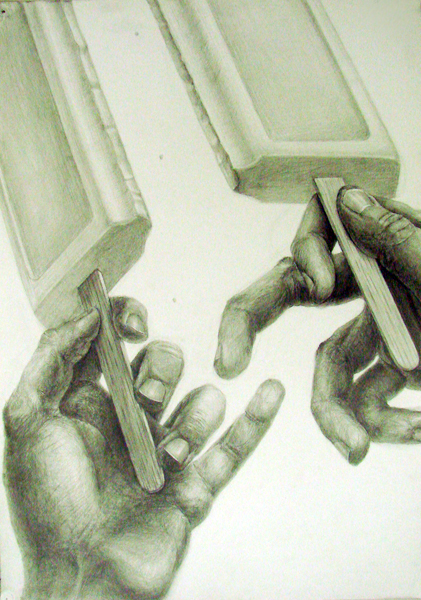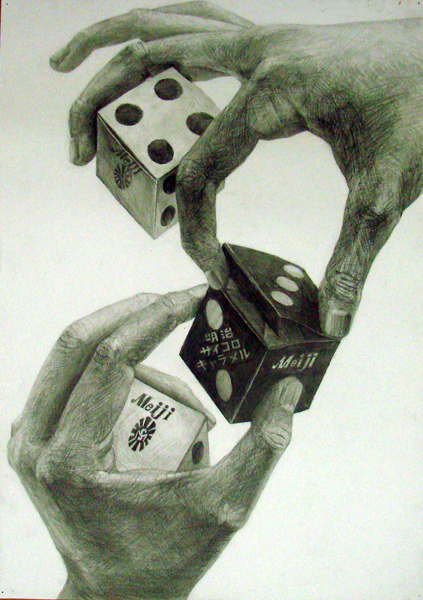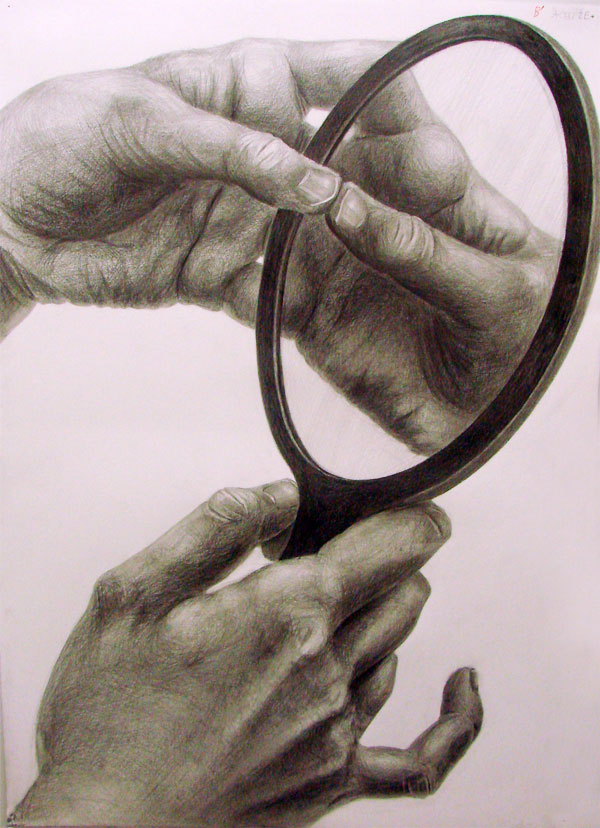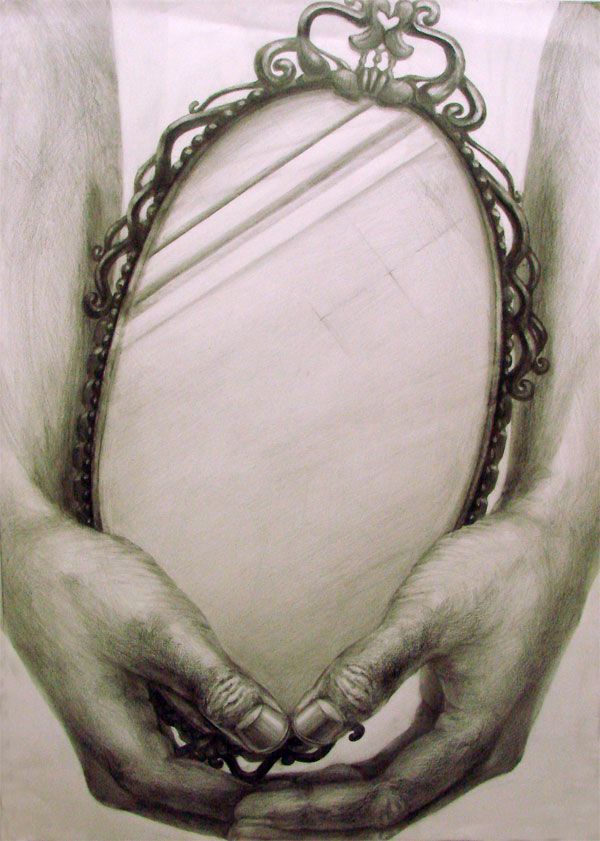※リンクの不具合修正しました!(9月20日)
はじめに
夜間部デザイン科の大島です。毎年4月くらいの時期に、デザイン科志望の受験生に「好きなデザイナーやデザインは?」という質問をしても「えーと、わかりません」と言う人がほとんどです。
ご家庭の方の職業がデザイン系だったり、学校が美術系でない限り、日本の高校生がデザインやデザイナーのことを知る機会というのはほとんどありません。
それなのに多くの学生がデザイン科に在籍しているというのは、前回のブログでも触れたようにサブカルチャーがデザインの入り口になっているからですが、入試や大学の勉強においてはきちんと本流の「デザイン」を理解していくことも重要です。
この日本において、デザインというものは身の回りに確かに存在しながらも、人々にとって身近で親しみがあるものとは決して言えないのが現状です。よって、デザインを理解したり好きになるためには、自ら積極的にデザインの世界に身を浸していく必要があるのです。
詳しい話は機会を見ながら平常授業のなかで話をしたいと思っていますが、とりあえずここでは平面に関するデザインを中心に「デザインを好きになるために、いかにして自らデザインに興味を持つか」という方法について書きたいと思います。
1.展示を観に行く
休みの日や学校が早く終わったときは美術館やギャラリーに足を運びましょう。アートであれ、デザインであれ一流のものを見ればセンスも身につきますし、美術館やギャラリーに行くとちょっと大人になった気がします。そして良いものを観た後は、決まって自分でもなにかを創作したい気持ちになるのです!どこでどのような展示が行われているかチェックするためには東京アートビートというサイトが便利です。以下はデザイン科の学生にオススメの施設ですが、展示の内容によっては他にいくつもあるので、参考程度に捉えてください。行ってほしい展示はその都度授業でお伝えします。
・ギンザ・グラフィック・ギャラリー
通称ggg(スリージー)。「ジージージー」と言ったりもしますが、オフィシャルな略称ではないかもしれないです。月1ペースの展示替え、無料、かつ質の高いデザインの展示。行かなきゃ損です。むしろ毎回行くべき。お願いだから行って下さい!新宿から銀座までは丸の内線で一本でいけますから!でも日曜日は休館日だから注意してくださいね。近くの資生堂ギャラリーとG8も是非一緒にまわりましょう。今開催中のPARTY、メディアアートっぽくて面白いですよ。
・21_21デザインサイト
デザインに関する展示専門の施設。以前は正直「?」という展示もなくはなかったのですが、最近は「これも自分と認めざるをえない」「テマヒマ」「デザインあ」など話題性のある展示が多く、デザインを学ぶ人なら展示が変わるごとにチェックしておきたいですね。今開催中のカラーハンティングも必見です。
・森美術館
六本木ヒルズの53階にある美術館。現代美術の展示が多いです。現代美術がデッサンや色彩構成に直接役に立つわけではないかもしれませんが、発想力の幅を広げるという意味ではどんどん観るべきでしょう。学生は1000円で展望台まで入れちゃうのでお得ですね。結構なデートスポットなので、ひとりで行くときは「俺(私)は純粋に美術が好きなだけだし寂しくなんかないし」という自己暗示が必要になります。
・東京都現代美術館
ここで今度、吉岡徳仁というデザイナー(最近はアーティストなのかな?)の展示が開催されるのでデザイン科ならば絶対チェックしたいところです。常設展やミュージアムショップも楽しいです。以前ここで芸人の東野幸治を目撃したことがあります。
・デザインHUB
ミッドタウン内にあるデザインの施設。無料。入り口がオフィスビルと一緒で周囲にはスーツの人が多く、本当にこんなところにデザイン施設があるのかとちょっと緊張します(私だけかもしれませんが)。展示ごとに毎回チェックする必要はありませんが、たまに結構いい展示してたりします。
・オペラシティアートギャラリー
新美からわずか5分程度。近いといつでも行けるような気がしてなかなか行かなかったりしますが勿体無いです。見て損することはないので時間があれば是非足を運びましょう。企画展はもちろん、コレクション展がなかなか渋いチョイスです。時間がなければ隣接したギャラリーショップで立ち読みをしてもいいし、同ビル内のICCはメディア表現に興味がある人は絶対行った方がいい場所です。
2.本屋に行く
デザインに関する知識やアイデアソースを得たければ本屋に行くことが近道です。といっても、そこらの本屋に行ったところでデザイン書籍はあまり充実していないのが実情です。ここでは高校生の皆さんが訪れやすい本屋さんを紹介したいと思います。美術系の本は総じて高いので基本は立ち読みです!どんどん手にとってみましょう。本当に欲しいものがあれば奮発して買ってもいいでしょう。
・青山ブックセンター
通称ABC。表参道のABCはデザイン書籍が揃っているので丸1日いても飽きません。近くにあるスパイラルの展示をチェックし、スタバでお茶をし、FoundMUJIで雑貨を見れば模範的なデザイン科の学生です。
・ブックファースト
新美からだとコクーンタワー店が近くて規模が大きいです。が、私は行ったことがありません!だって広すぎるし…。ルミネ新宿店はそこそこ充実している上、座り読み用のイスまであるので、もっぱらそちらを利用しています。私と会わないといいですね。
・リブロ
店舗によってデザイン書籍の充実度は違うかもしれません。おすすめは系列店の洋書を扱うロゴスが併設されている店舗です。都内だと吉祥寺か渋谷でしょうか。ロゴス渋谷は立ち読みをし、気になった作家などの名前をメモり、家に帰ってネット検索をした学生時代の思い出の場所です。
・紀伊国屋
いわずと知れた大型書店。でもここも大きすぎて自分はあまり利用しないかな…。新美から遠くなったし…。でも高校時代、わけもわからずに購入した柳宗理の本はいまでも大切にしています。
・TSUTAYA 六本木
六本木ヒルズの森美術館やミッドタウンの21_21デザインサイト、デザインHUBなどを観た帰りなんかにフラッと立ち寄るといいです。六本木という欲望が渦巻くスポットで、ギラギラとした人々に囲まれながら、オシャレな雑誌を読んでいると、様々な疑問が去来します。
3.デザイン誌を読む
この世にはファッション誌やゲーム誌があるように、デザインに関する雑誌というのもあるんです。最初は何が面白いかもわからないかもしれないけど、ペラペラめくりながら、なんとなくカッコいいな、みたいなことを感じればいいんじゃないでしょうか。洋書屋やギャラリーショップなんかに置いてある海外のデザイン関係の本もオススメです。最初はそうやって「意味はよくわからないけどデザインに興味あって洋書とか読んじゃっている私」に酔えばいいのです。みんなそういう過程を経ています(多分)。
・アイデア
・+81
4.デザイナーを知る
デザインの世界をより深く知るためには、デザインをする人、すなわちデザイナーの名前も知ると良いでしょう。皆さんが日常的に目にするポスターやパッケージやロゴなども実は著名なデザイナーが手がけていたりするのです。とりあえずデザイン科ならば知っておきたい、日本の代表的なデザイナーの名前を紹介します。(独断で選んだので「なんでこのデザイナーが紹介されてないんだ!」などあるかと思いますが…)
【日本の代表的なデザイナー】
田中一光
亀倉雄策
福田繁雄
永井一正
勝井三雄
粟津潔
仲條正義
大貫卓也
佐藤可士和
原研哉
佐藤卓
葛西薫
中島英樹
野田凪
服部一成
佐野研二郎
水野学
菊地敦己
グルーヴィジョンズ
森本千絵
長嶋りかこ
【もうちょっと背伸びしたい人に】
William Morris(ウィリアム・モリス)
Eric Gill(エリック・ギル)
Kasimir Malevich(カジミール・マレーヴィチ)
Wassily Kandinsky(ヴァシリー・カンディンスキー)
Piet Mondorian(ピエト・モンドリアン)
Man Ray(マン・レイ)
Hans Arp(ジャン・アルプ)
El Lissizky(エル・リシツキー)
Alexandre Rotchenko(アレクサンドル・ロトチェンコ)
Paul Klee(パウル・クレー)
Jopsef Albers(ヨゼフ・アルバース)
Herbert Bayer(ヘルベルト・バイヤー)
Joost Schmidt(ヨースト・シュミット)
Josef Müller-Brockmann(ヨゼフ・ミューラ=ブロックマン)
Max Bill(マックス・ビル)
Otl Archer(オトル・アイヒャー)
Armin Hoffmann(アーミン・ホフマン)
Max Huber(マックス・フーバー)
Walter Allner(ウォルター・アルナ―)
McKnight Kauffer(マックナイト・カオファー)
おわりに
本当はもっと具体的な作品なども紹介したかったのですが、あまりに長くなってしまいそうなのでとりあえず今回はこのあたりで区切ります。
いま新美に通っている方は、ほとんど東京かその周辺地域にお住まいだと思います。
ちょっと足を伸ばせば大きい本屋や美術館がいくつもあって、それは全国の美大受験生からすればずいぶんと恵まれている環境といえるでしょう。あまりにも身近にありすぎるため、そのアドバンテージに気がついていない人も多いのですが、利用しない手はないでしょう。
今後の夜間部私大系の授業では、制作のあいだにデザイナーの紹介やデザイン史、あとは皆さんが好きそうな映像などを見せる機会を設ける予定です。皆さんが少しでもデザインが好きになってくれることを願っています。